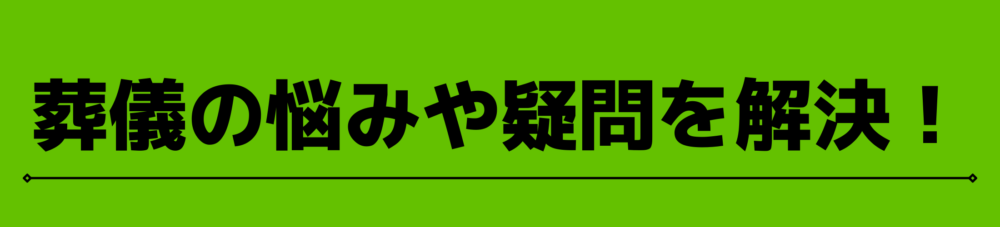- 四十九日の香典っていくらぐらいが相場なんだろう?
- 孫の場合だと香典は必要ないのかな?
- 四十九日の香典の表書きって御霊前と御仏前どっち?
こんな疑問に答えていきたいと思います。
この記事でわかる事
- 四十九日の時の香典の相場
- 香典袋の選び方や水引の色
- 四十九日の時の香典の渡し方とタイミング
- 四十九日の香典マナー
- 香典と一緒に持っていくお供物について
四十九日には、香典を持って行くのが一般的。
ですが、香典の相場や渡すタイミング、香典袋の種類など分からないという事も多々あります。
また、香典と一緒に持っていくお供物についても「何を持っていけばいいのか分からない」という場合が多いです。
そこで今回は、四十九日の香典について解説していきます。
この記事を読めば「四十九日法要の香典の相場」について理解することができます。
四十九日法要の香典の相場はいくら?(パターン別で紹介)

香典の相場は、故人との関係性や会食があるかで変わってきます。
また、会食の用意がある場合は、お食事とお礼の品が用意されている場合がありますので、その分金額を余計に用意する必要があります。
- 故人が親の場合
- 故人が祖父や祖母の場合
- 故人が親戚の場合
- 故人が兄弟や姉妹の場合
- 故人が友人や知人の場合
上記の場合での香典の相場を解説していきます。
故人が親の場合
故人があなたの親だった場合の香典の相場は、1~10万円という風になっています。
金額に開きがありますが、これは年齢などで包む額が変わってくるからです。
- 20代〜30代で1〜5万円。
- 40代からは上限が10万円程度となっています。
会食や仕出し弁当がある場合は、5千円〜1万円上乗せするようにしましょう。
故人が祖父や祖母の場合
故人があなたの祖父や祖母だった場合の香典の相場は、5千円~3万円となっています。
この場合も年齢によって包む額が変わってきます。
- 20代で5千円〜1万円。
- 30代で5千円〜2万円。
- 40代で5千円〜3万円。
という風になっています。
会食や仕出し弁当がある場合は、5千円〜1万円上乗せするようにしましょう。
故人が親戚の場合
故人があなたの親戚だった場合の香典の相場は、5千円~3万円となっています。
この場合も年齢によって金額が変わってきます。
- 20代で3千円〜1万円
- 30代で5千円〜2万円
- 40代で5千円〜3万円
という風になっています。
会食や仕出し弁当がある場合は、5千円〜1万円上乗せするようにしましょう。
故人が兄弟や姉妹の場合
故人があなたのご兄弟だった場合の香典の相場は、3~5万円となっています。
この場合も年齢によって包む額に開きが出てきます。
- 20代・30代で3万円
- 40代で5万円
というふうになっています。
会食や仕出し弁当がある場合は、5千円〜1万円上乗せするようにしましょう。
故人が友人・知人の場合
故人があなたの友人や知人だった場合の香典の金額は、3千円~1万円となっています。
この場合も年齢によって包む額に開きが出てきます。
- 20代で3千円〜5千円
- 30代・40代で3千円〜1万円
というふうになっています。
会食や仕出し弁当がある場合は、5千円〜1万円上乗せするようにしましょう。
四人家族の場合の四十九日の香典はいくら?

義母の四十九日法要に家族4人で参加するんだけど、香典っていくら包めばいいのかな?
引き出物が無いのであれば1人10,000円で4万円包んで、2,000〜3,000円のお供物を持っていけば問題ありません。
子供がまだ成人してない場合は、子供の分は2人で10,000円としても大丈夫です。
四十九日の香典は、食事代を参加者が負担する仕組みです。
参加者が多ければ、香典の金額も変わってきますが、基本的には1人1万円と思っておいていいでしょう。
四十九日の香典をいらないと言われた時は

四十九日は香典いらないって言われたんだけど、どうしたらいいのかな?
四十九日法要で「香典不要」のお知らせがあった場合は、無理に渡す事はせずに、遺族側の意見を尊重しましょう。
「どうしてもお世話になったから渡したい」という気持ちもあると思いますが、強引に渡してしまうと遺族側もお返しの準備などがあり、負担となってしまいます。
もし、どうしても弔意を表したい場合は、供物や供花を贈るといいでしょう。
供花についての詳しい解説は以下の記事でしています。
こちらもCHECK
-

-
【これで失敗なし】四十九日に贈る花の相場や大きさを紹介!
続きを見る
香典袋の選び方や水引の色は?

四十九日に参加するときに持って行く香典ですが、以下4つの注意点があります。
- 香典袋の表書き
- 水引の色
- 水引の結び方
- 水引の本数
1つずつ解説していきます。
香典袋の表書き
宗派によって変わってきますが、相手方の宗教が仏教の場合だと「御仏前」と書かれた不祝儀袋を選ぶようにしてください。
もし、相手型の宗教が分からない場合は、「御香典」「御香料」と書くようにしましょう。
御香典や御香料は「お香の代わりとして」という意味合いがあって、どの宗派の場合でも使用する事ができます。
メモ
- 神式の場合は「御神前」「御玉串料」「御榊料」と書きます。
- キリスト教(カトリック)の場合は「御花料」「御ミサ料」と書きます。
- キリスト教(プロテスタント)の場合は「御花料」「献花料」「弔慰料」と書きます。
水引の色
- 仏教の場合で1,000〜5,000円を包む場合は白黒の水引。
- 10,000〜50,000円の場合は黄色白の水引。
- 50,000円以上を包む場合は、双銀の水引を選んでください。
ない場合は、白無地か蓮の絵柄が書かれたものが一般的です。
メモ
- 神式の場合は、黒白か双銀、白銀か白無地のものを選んでください。
- キリスト教の場合は、白無地か十字架、白百合の描かれたものを選んでください。
- 宗教がわからない場合は、白黒か双銀のものを選んでください。
水引の結び方
水引の結び方は、「結び切り」か「あわじ結び」の2種類があって、一般的に使用されているのは「あわじ結び」です。
あわじ結びは「同じ事が起きないように」という意味と「末永く付き合う」という意味が込められた結び方で、お布施などにも使われています。
水引の本数
水引の本数は基本的には5本となっています。
例外として、格式を重んじる場合は7本。
10万円以上を包む場合に10本にすることもあります。
香典袋の名前の書き方

香典の名前の書き方については以下の記事で解説しています。
-

-
参考香典袋の書き方マナーを紹介!中袋がない時の住所は横書きでもいいの?
続きを見る
四十九日の香典は薄墨を使わないといけない?
「四十九日」「一周忌」「三回忌」などは予定が決まっている事なので、薄墨を利用しなくても問題ありません。
ボールペンやサインペンで書く方もいますが、ボールペンやサインペンは略式となるので、可能であれば濃墨で書くようにしましょう。
四十九日の香典マナー

四十九日の香典を包むにあたって気を付けたい点は以下の2つです。
- 新札を包んでいいのか
- 包んではいけない金額があるのか
- お札の向き
- 香典の包み方
1つずつ解説していきます。
新札は使ってもいいの?
マナーとしては、新札を使っても構いません。
お通夜、告別式で新札を使ってはいけない理由は2つ。
「突然のことで新札を用意する時間がなかった」
「あまりに急だったため、新札を用意する時間ももったいなく、会いに来ました」
という意味が含まれています。
四十九日法要は事前に日時が決まっており、案内をいただきますので新札でも失礼には当たりません。
ですが、一般的には悲しみの席では新札を避ける、というイメージがありますので旧札でも構いません。
包んじゃいけない金額
4や9といった死や苦しみを連想させる数字の金額は避ける傾向にあります。
1、2、3、5、10を使うのが一般的ですね。
お札の向き
お札の向きは全て揃えるのが基本となります。
上下、裏表すべて揃えて、人物の肖像画が印刷されている面が「表」となります。
詳しい内容は以下の動画をご覧ください。
香典の包み方
香典は袱紗(ふくさ)に包んでお渡しするといいでしょう。
袱紗の色は弔事でも慶事でも使える「紫」が無難です。
袱紗の包み方は以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもCHECK
-

-
葬儀で使う袱紗(ふくさ)の色と正しい包み方を紹介!ない時の代用品は何を使う?
続きを見る
香典を渡すタイミングはいつ?

お通夜、告別式と違って特別に受付などを用意していないことも多いので、戸惑われることも多いでしょう。
また、場所もご自宅、寺院など、式場と多岐に渡ります。
いずれも到着したらすぐにご遺族に一声かけて香典をお渡しすると良いでしょう。
近い身内であっても、ご遺族は亡くなってから四十九日までは気が抜けないものですので、ねぎらいの言葉をかけると良いですね。
香典と一緒に持っていくお供物について

香典と一緒に持っていくお供物って何がいいんだろう?
香典と一緒に持っていくお供物でよく選ばれているのか以下の4つです。
- 線香
- 果物
- お菓子
- 花
- 故人が好きだったもの
香典もお供物も高価なものになると、遺族の負担となってしまうので、双方のバランスを見つつ、香典が1万円ならお供物は少しグレードを落とすなど工夫をしましょう。
四十九日のお供物については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
お通夜、告別式に比べたら少しカジュアルな雰囲気ですが、マナーはしっかりと守って参列したいものですね。
四十九日まではご遺族は大変気苦労をされるものです。
お疲れ様の気持ちを持って参列され、故人がいなくなった悲しみからひと段落する1日になると良いですね。