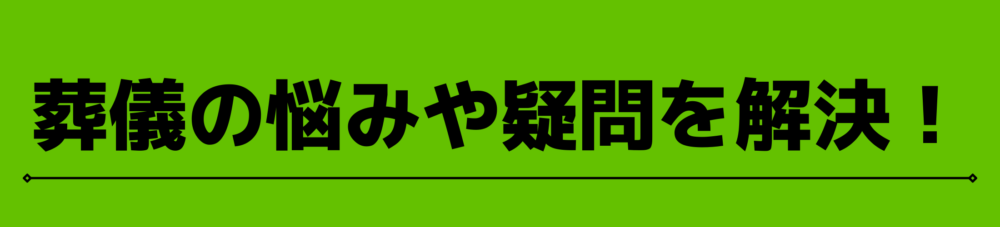- 四十九日のお供物って何を持っていけばいいのかな?
- お供物の金額相場ってどのぐらいなんだろう?
- 熨斗(のし)の表書きも知りたいな。
こんな疑問に答えていきたいと思います。
四十九日法要とは、故人の命日から49日目に執り行われる法要です。
「法要」とは僧侶を呼んでお経をあげてもらい、故人の冥福を祈ることで、「法事」とは法要後の焼香、会食を合わせた総称です。
いずれにしても故人を偲び親族、親しい友人が集まって執り行う大切なセレモニーです。
お通夜、告別式ほどではないですが参列者は香典と共にお供え物、お供花を用意して供養します。
最近では「御供物料」として品物は用意せずに現金を包むことも多くなっています。
反面、地域によってはお供え物を最後に出席した人たちで分け合うという風習があり、お供え物が必ず必要というところもあります。
地域のしきたりはそれぞれ違いますので、事前に親族や年配者などに確認しておきましょう。
この記事でわかる事
- 四十九日のお供物の金額相場
- 四十九日のお供物は何を持っていけばいいのか
- 熨斗(のし)の表書きについて
- 四十九日に香典とお供物を両方準備するべきか
- お寺で四十九日法要をする際のお供物
この記事を読めば、四十九日法要の際のお供物の疑問がなくなります。
四十九日のお供え物の相場はいくら?

四十九日法要のお供え物の相場には、以下の2通りがあります。
- 親しい関係性だった場合は5,000〜1万円ほど
- 会社関係や知人の場合は、3,000〜5,000円ほど
これらはあくまでも目安ですので、ここを基準として検討すると良いでしょう。
あまりに高額すぎると、ご遺族にいらない負担をかけてしまうことにもなりかねません。
不安な場合は年配者やご両親などに相談して決めると良いですね。
四十九日のお供え物は何を持ってく?

四十九日法要の際のお供物は「消費してなくなってしまうもの」がいいとされています。
消え物が良いとされている理由は「不祝儀が残って悲しい気持ちを引きずらないように」という所からきていて、食べ物や消耗品が定番です。
主に選ばれているお供物は以下の5つ。
- 線香
- 果物
- お菓子
- 花
- 故人が好きだったもの
線香

法要時にお線香を持参するのは日本の昔からの習慣のひとつです。
「香典」とは香りを買うための費用として包まれたという説もあります。
故人の冥福のためには「香り」を欠かせないこと、香りによって身を清めるという考え方もあり仏教上、最も良いご供養になると言われます。
また、香典と共に持参する場合も多いです。
四十九日法要の香典についてこちらで解説しています。
果物

「お供えものには、丸いものが良い」とも言われ、季節の果物は四十九日法要に限らず、お供え物の定番です。
果物は参列者で分け合えるので、お供物としては重宝されています。
果物店、スーパーなどでも詰め合わせや盛り籠が用意されていますので、購入が身近なのも嬉しいところです。
お供えに適しているといわれる果物は、バナナ、リンゴ、ぶどう、みかんなどです。
他には季節の果物、メロンやいちごなどがあっても良いですね。
長持ちしないもの、果汁が出やすいものは避けるようにしましょう。
お菓子

和菓子も洋菓子もお供え物の定番ですね。
後に集まった人たちで分けられるよう、日持ちのする小分けのものが良いでしょう。
洋菓子ならクッキーなどの焼き菓子、和菓子なら最中や羊羹が良いでしょう。
小豆を使ったお菓子は日本ではお供えものの定番として昔から大切にされています。
菓子店やスーパー、デパートやコンビニなどでも取り扱っていますので手軽に手に入るのも助かります。
小包装になっているものを選ぶと、持ち帰りやすく間違いないでしょう。
ただし、生クリームのついたものは避ける傾向があるようですので気をつけましょうね。
花

仏壇に花は欠かせませんので、花はいくらいただいても嬉しいものです。
四十九日までは忌中となりますので、四十九日法要で用意するお供花は白が基調のものとなります。
そのまま飾れるアレンジメントが主流ですが、四十九日から喪が明けることもあり、ブリザーブドフラワーなどを送る場合もあります。
ただ、宗教、宗派や地域によって習慣が異なりますのでよく調べてから用意するようにしましょう。
饅頭

お饅頭もお供えの代表のひとつですね。
地域によっては白、黄色、緑、ピンクなどカラフルなものをお供えするところもあります。
法要終了後に参列者で分けられるのも昔から重宝される理由のひとつでしょう。
法要時に手作りのお饅頭やお餅は欠かせない、というところもあるようです。
お供え物といったらお饅頭、といっても良いかもしれません。
故人の好きだったもの

あまり深く考えずに、故人の好きだったものを用意するというのも多くなってきました。
お酒やお菓子などが多いようですね。
生クリームを使用したものは選ばないのがマナーですが、この場合はその限りではありません。
故人が好きだったものをお供えしてあげたい、という気持ちはきっとご遺族も喜んでくださるはずです。
選んではいけないお供物の品

お供物だからといって、何でも選んで良いわけじゃなく、選んではいけないものも存在します。
それが以下の4つ。
- 肉や魚
- 傷みやすい食べ物
- 棘がある花や香りの強い花
- 遺族がお酒を飲まない場合のお酒
上記の4つは、お供物としては不向きなものなので、選ばないように注意しましょう。
お供物に熨斗(のし)は必要?表書きについても

お供物の用意ができたら「熨斗(のし)」は必ず掛けましょう。
四十九日法要では、黒白か双銀の水引が一般的です。
地域によっては黄白の水引を使うところもありますので、お供え物を用意する際に担当の方や、近隣の年配者の方などに確認するようにしましょう。
熨斗(のし)の表書き
熨斗の表書きは以下の通りです。
- 仏教では「御仏前」
- その他は「御供物」「供物」
稀にですが、お供物の表書きに「御霊前」と記してしまう場合がありますが、これはマナー違反となってしまいます。
本来、四十九日法要を境に仏となり極楽浄土へ旅立つとされているからです。
「御供物」の下には名前をフルネームで記載します。
姓のみを書く方もいらっしゃいますが、受け取り手からすると「誰なのか」判断しにくくなる場合があります。
なので、姓しか書けない理由がないのであれば、基本はフルネームで書くようにしましょう。
連名の場合は並べて記載しますが、5名以上の場合は「一同」とするのが一般的です。
また、名前を書くときに使う墨は濃い色のものを使いましょう。
お通夜や葬儀では「薄墨」を使いますが、四十九日法要は日取りがあらかじめ把握できているので、薄墨を使用しなくても問題ありません。
四十九日に香典とお供物を両方準備するべきか

四十九日には香典とお供物の両方を準備した方がいいのかな?
四十九日法要に参列する際は、香典とお供物の両方を準備する方がいいでしょう。
香典とお供物を合わせた金額でバランスを取る方が多く、香典を準備するのであれば、お供物の金額は抑えて四十九日法要に参列するようにしましょう。
香典もお供物も高価な場合は、遺族側の負担となることもあるので注意が必要です。
お寺で四十九日法要をする際の果物はどれぐらい必要?

お寺で四十九日法要をするんだけど、お寺に供える果物ってどのぐらい必要なのかな?
お寺で四十九日法要を執り行うとなると、自宅とは違い「何をどのぐらい準備したらいいのか分からない」という状況になりやすいです。
豪華なカゴ盛りがいいのか、自宅で法要する時のような果物でいいのかなど。
結論、お寺で四十九日法要をする際でもカゴ盛りなどは必要なく「お盆にのる程度」の果物で問題ありません。
法要後は参列者で分けて持って帰るので、分けきれない量の果物だと食べ物を粗末にしてしまいますし、費用もかかってしまいます。
初めての法要だと迷う事も多いですが、お寺で法要する際の果物に関しては深く悩む必要はありません。
四十九日法要をしない場合のお供物

四十九日法要はしないみたいだけど、お供物もいらないのかな?
無宗教の場合は、四十九日や一周忌など法要の場を必ず設ける必要はないので、中には法要を全くしない方も居るかと思います。
しかし、年に1度だけでもいいので故人と親しかった方だけでも呼んで、故人を偲ばれてもいいでしょう。
その際は凝った物じゃなくてもいいので「故人の好きだったもの」を準備してあげて、皆さんで食事などをしつつ故人の思い出話をしてもいいかもしれないですね。
四十九日法要に参列する際の服装

四十九日法要に参列する際の服装は以下の通りです。
男性の場合
- ブラックフォーマル
- 白の無地ワイシャツ
- 黒の無地ネクタイ
- 華美な飾りのついてない黒い靴
- 適度な装飾や大きすぎないメンズの時計
女性の場合
- 露出や光沢のない黒のアンサンブル、ワンピース、スーツ
- インナーの色は黒
- スカートの丈は膝が隠れる長さのもの
- ストッキングや靴も黒色
- アクセサリーは真珠と結婚指輪ならOK
- メイクは薄化粧が基本
まとめ
いかがでしたでしょうか?
お供え物を持参した際には、仏壇に直接持って行かずに、かならずご遺族にお渡ししましょう。
その際は「本日はお招きいただき、ありがとうございます」など、四十九日法要のご案内をいただいたお礼と共に故人への供養の気持ちを示しましょう。
細かいマナーですが、ご遺族を不快な想いにさせないよう、気をつけたいものですね。