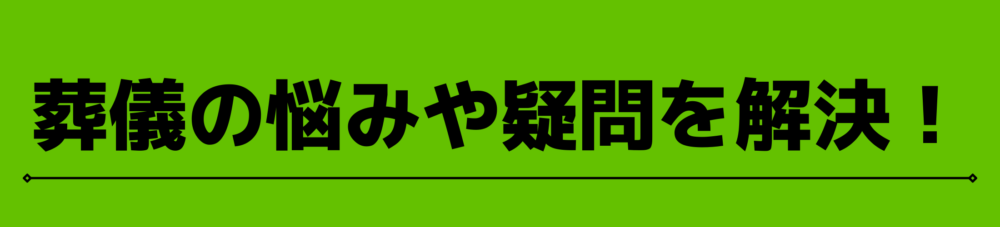こんな疑問に答えていきたいと思います。
この記事でわかる事
- お布施袋の表書き(宗派別)
- お布施の相場
- お布施に新札を使ってもいいのか
- お布施の正しい渡し方
- 四十九日と納骨式が同時の場合のお布施
- お布施以外にかかる費用
近頃、葬儀や法要の場でよく「四十九日法要でどれくらい包んでお坊様にお渡しすればいいですか?」というお悩みを聞きます。
あくまで「お気持ち」ですので、厳密な取り決めや費用が決まっているわけではありません。
しかし以前よりもお寺との交流が少なくなった近頃では、そういったことを教えてくれる場所や機会が減りお悩みになっている方は多いと思います。
そんなお悩みの方のために、今回はお布施の正しい書き方・相場・マナーなどを宗派別にご紹介いたします。
この記事を読めば、四十九日のお布施の疑問が解決します。
お布施袋の表書きについて!宗派別に解説!

表書きとは、お布施を渡す時のお札を包んだ封筒・半紙などの表面に書く文字のことを指しています。
お布施は故人のために読経してくださったお坊様へのお礼であり、そのお布施の表書きは「ただ書けばいいもの」ではないことはご存知でしょうか?
お布施の表書きにも正しいものと正しくないものがあり、宗派によって書き方も変わってきます。
そんな表書きの正しい書き方を下記の宗派別にご紹介いたします。
- 真言宗
- 浄土真宗
- 曹洞宗
- 仏教
- 神道
- キリスト教
- 無宗教
- 天台宗
- 日蓮宗
真言宗
真言宗では「御布施」「お布施」と上段中央に書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書きます。
「御経料」「御礼」とは書きませんのでご注意下さい。
また、表書きを記さずにお渡しする場合もあります。
浄土真宗
浄土真宗では「御布施」「お布施」と上段中央に書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書きます。
また表書きを記さずにお渡しする場合もあります。
しかし、浄土真宗ではお布施を仏様への感謝の気持ちを示したものとしているため、僧侶個人や寺院への謝礼を意味する「志」「寸志」などは使ってはいけません。
マナーに反しているのでご注意下さい。
曹洞宗
曹洞宗では「御布施」「お布施」と上段中央に書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書きます。
また表書きを記さずにお渡しする場合もあります。
仏教
仏教では上段中央に「御礼」「お布施」「読経料」「御回向料」と書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書くのが一般的です。
また表書きを記さずにお渡しする場合もあります。
神道
神道では上段中央に「御礼」「御祈祷料」「御祭祀料」「御榊料」「御神饌料」「玉串料」と書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書きます。
キリスト教
キリスト教では、教会宛の場合は上段中央に「献金」「記念献金」「感謝献金」「ミサ御礼」「御ミサ料」と書き、神父・牧師宛には「御礼」と書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書きます。
無宗教
無宗教では、故人の遺志や遺族の意向により自由な形式で葬儀が行えるため、法要やその他行事に関しては他宗教とは異なります。
四十九日法要もどうするかは故人・遺族の自由ですので、もしお坊様をお呼びしての法要でしたら各宗教にあわせた表書きをすることをお勧めします。
天台宗
天台宗では上段中央に「御布施」「お布施」「御礼」と書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書きます。
また表書きを記さずにお渡しする場合もあります。
日蓮宗
日蓮宗では上段中央に「御布施」「お布施」「御礼」と書き、下段に喪主もしくは葬家の名前を書きます。
また表書きを記さずにお渡しする場合もあります。
お布施の相場はどのぐらい?

お布施はあくまで仏様やお坊様への「お気持ち」ですので、「お布施は○○円」とは決められるものではありません。
「いくら包めばいいのか」「多く包む方がいいのか」「少ないと無礼にならないか」など、多くの方がお布施の相場で悩んでいらっしゃいますが、厳密に言えばお布施の相場は決まっていません。
ですが、ある程度の相場はあり、「四十九日法要のお布施の場合は各宗教3~5万程度」のお布施を包みます。
ただし、地域やお寺によってはそのお布施の値段も変わってくるので、不安な場合は事前に住職にお布施の金額を聞くなどすることをお勧めします。
お布施に新札は使ってもいいの?

結論から先に言うと、四十九日のお布施は新札を使っても問題ありません。
お通夜や葬儀でのお布施は、新札がNGとされていますが、事前に日程が分かっている四十九日法要などは、新札を使ってもマナー違反とはならないのです。
新札がない場合は、なるべく「汚れのない、ヨレヨレしてないお札」を使用するようにしましょう。
お布施の正しい渡し方を紹介

何にでもそうですが、誰かに何かを渡す時はそれなりのマナーがあります。
お布施のように感謝を込めて渡すものであれば尚更です。
ここからはお布施の正しい渡し方をご紹介します。
いつ渡すの?
一般的には法要の前か後が好ましいとされています。
合同での法要の場合は本堂入口付近に受付がありますので、本堂に入る際に受付の方にお布施をお渡しします。
もし受付がない場合で法要が始まるまでに時間があれば、法要をしてくださる僧侶へ挨拶を兼ねてお布施をお渡ししましょう。
その際には一言お礼を添えるなどした方が良いでしょう。
法要前で時間がない場合は、法要を終えた後にお礼の挨拶の際にお布施を渡ししすると良いでしょう。
お布施を渡す際の正しい向き
ただ渡せばいいというものではなく、お渡しする際にも手順があり正しい向きがあります。
それを怠っては相手への無礼と取られてしまいますので、この機会に正しいお布施の渡し方をご紹介いたします。
1,準備
まずはお布施を切手盆に置くまたは袱紗(ふくさ)の包みを解き用意します。
このときは自分が文字を読める方向に持っています。
2,切手盆・袱紗の向きを変える
右上と左下を持ち時計回りに90度回させ、更に上下を持ち替え90度回しお坊様(または神主様もしくは神父・牧師様)が文字を読める向きにします。
3,差し出す
お礼の口上を述べた後にお渡ししましょう。
作法やマナーは各宗教や個人によって異なったり入り混じったりしており、「これが正しい」とは言い切れません。
ですが心を込めた感謝の気持ちがあれば、間違っていたり多少の無作法があったとしても感謝の気持ちは伝わります。
四十九日と納骨式が同時の場合のお布施

四十九日と納骨式を同時に行う場合は、四十九日法要のお布施と納骨式のお布施を合わせて渡します。
金額の相場は50,000〜100,000円になることがほとんどです。
また、四十九日法要のお布施は宗派によって変わるので、宗派ごとのお布施の相場は下記の表の通りです。
| 曹洞宗 | 葬儀の際に渡したお布施の1割 |
| 真言宗 | 30,000〜100,000円 |
| 浄土真宗・浄土宗 | 30,000円ほど |
| 日蓮宗 | 50,000円ほど |
| 臨済宗 | 30,000〜50,000円ほど |
| 天台宗 | 30,000〜50,000円ほど |
ただ、金額の相場と言えども、地域によっては上記の相場よりも高い場合、低い場合があるので、表の相場を目安に地域の方に聞いてみるようにしましょう。
お布施以外にかかる費用

お布施の他に僧侶にお渡しするお金はないのかな?
お布施以外にかかる費用は下記の2つです。
- お車代
- 御膳料
お車代は「足を運んでくれた対価」として、御膳料は「僧侶が会食のおもてなしに参加できない代わりに渡すお礼」となります。
お車代の相場
お車代の相場は5,000〜1万円となっています。
これは、市内や近隣市外での移動の際の相場となっていて、遠方から新幹線や飛行機などで来る場合は、実費をあらかじめ調べて相応の金額を用意しましょう。
御膳料
御膳料の相場は5,000〜1万円となっています。
僧侶が複数名で来る場合は、人数分の御膳料を包むのですが、その際に個別に渡すのではなく「1つの袋にまとめる」ようにしましょう。
もし、会食に僧侶が参加するのであれば御膳料は必要ありません。
まとめ
お布施の目的はきて頂いたお坊様への感謝の形です。
作法やマナーばかりに気をとられ、感謝の気持ちを忘れ形だけになってしまうよりかは、多少の無作法やマナー違反であっても真心を込めお布施を渡す方が相手にも気持ちがより伝わると思います。
宗派や宗教によって大きく変わる部分もあり混乱しそうになる場面もありますが、そんな時にこの記事を参考にしていただけたらと思います。