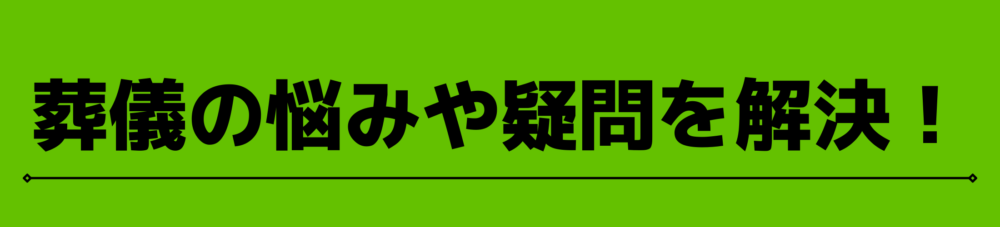お通夜も葬儀も欠席してしまったんだけど、香典だけ遅れて渡すのは失礼になるのかな。
こんな疑問に答えていきます。
ある日突然訃報を受けても、通夜や葬儀・告別式への参列がどうしてもできないことがあります。
通夜か葬儀・告別式のどちらかに出席できればまだいいですが、どちらにも参列できない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
また、葬儀を欠席した際の香典マナーのお話しをしていきたいと思います。
※この記事でわかる事※
- 葬儀に参列できない時の対応
- 葬儀に出れなかった時の香典の渡し方
葬儀に参列できない場合はどうしたらいい?

基本的に葬儀などの弔事は、結婚式などの慶事よりも優先されます。
やはり葬儀は故人にとっては一生に一度の日で、故人に別れを告げる最後の日となりますので、慶事よりも優先されることが一般的な常識となります。
訃報を受けた時に参列できないことが分かっている場合は、その場で参列できない旨を伝えましょう。
詳しい内容は以下の記事で解説しています。
葬儀に出れなかった際の香典の渡し方と注意点

葬儀に参列できず、香典だけを遅れて渡す際には3つの方法があります。
- 香典を郵送する
- 代理人に預ける
- 後日、弔問に伺う
1つずつ解説していきます。
1.香典を郵送する
香典を郵送する際に大事なポイントは5つです。
①香典の金額に合った香典袋を用意し、現金を入れます。
この時に新札を使うことは、訃報が来ることを予定して準備していたと思われるので避けましょう。
どうしても新札しかない場合は、折り目をつけると良いでしょう。
②現金書留を用意します。
現金書留は郵便局で購入できます。
「書留」には、一般書留、簡易書留、現金書留の3種類があり、書留の種類によって料金や保証される金額も変わってきます。
現金書留の場合、郵送料金は430円で損害要償額は1万円までです。
保障金額を増やす場合は、5千円ごとに10円の追加料金がかかります。
また、上限は50万円までとなっています。
現金書留にも2種類のサイズがあります。
小さい方:約119×197㎜ 約8.5g
定形郵便物 21円
大きい方:約142×215㎜ 約10.7g
定形外郵便 21円
送る香典袋などの大きさに合わせて購入しましょう。
現金書留の封筒の購入や手続きは、郵便局で行います。
③宛先は喪主の方の名前で送ります。
現金書留の封筒にはもちろんですが、香典袋にも必ず氏名と住所を書くようにしましょう。
④葬儀に参列できなかったことへのお詫びやお悔やみの言葉を手紙に書いて同封しましょう。
使用する便せんや封筒は、一般的に白地のものが良いとされています。
もし白地のものがない場合は、シンプルで落ち着いたデザインや色のものを選びましょう。
字が汚いからといってパソコンなどで文字を打つことはやめ、必ず手書きで書くようにしましょう。
どんな字でも、やはり手書きの方が書き手の気持ちが伝わります。
2.代理人に預ける
自分が参列できない場合、他の参列者に預けるという方法もあります。
香典は世帯ごとに包むのが基本ですので、親や配偶者の代理として香典を預かることも多くあります。
家族以外の職場の同僚や友人に預けることもできます。
代理人に預ける場合のマナーや注意点は以下の2通りです。
①預ける代理人に受付での記帳もお願いすることになるので、自分の氏名・住所をきちんと伝えておきましょう。
また、代理人に預ける場合は、自分の氏名の左下に「内」と書くことで代理人が持参したことをわかるようにしておくと、遺族側が情報を整理しやすくなります。
②代理人に預ける場合でも、後日、参列できなかったお詫びとお悔やみの言葉をきちんと伝えることを忘れないようにしましょう。
3.後日うかがう
葬儀が終わった後でも、弔問してお参りをすることで弔意を表すことになります。
後日うかがって香典を渡す際のマナーや注意点は以下の3通りです。
①葬儀後に自宅などに弔問して香典を渡す場合は、必ず電話などでご遺族の都合を確認するようにしましょう。
葬儀後しばらくの期間は遺族側は何かと忙しい時期でもありますし、なにより故人を亡くされた悲しみの中にいることを考慮しましょう。
②喪服や真っ黒な服は避けましょう。
弔問する際に、喪家へ訪問するから喪服や黒い服を着ていこうと思われる方も多いかもしれませんが、葬儀や法事ではありませんので喪服や真っ黒な服は着用しないのがマナーです。
「黒色」は喪服や葬儀を連想させる色ですので、葬儀が終わって少しずつ日常を取り戻しつつあるご遺族の心情を考慮しましょう。
かといって派手な服装や露出の多いデザイン、普段着すぎる服装ではかえって失礼ですので注意しましょう。
③少額の供物を持っていきましょう。
弔問の際、手ぶらで行くのも良くないですが、かといって高額なものやあれこれ持っていくことはご遺族の気を遣わせてしまうことにもなりかねません。
「香典返し」の必要のない程度の金額の供物、果物やお菓子、お花などが良いでしょう。
供物については以下でも詳しく紹介しています!
【まとめ】葬儀を欠席した際の香典マナーを紹介!遅れて渡すのは失礼?
訃報を受け取るときはいつも不意にやって来ます。
誰しもが予期できるものではありません。
そのため、故人との最後のお別れとなる葬儀ですが、やむを得ない事情で参列できないことはあるかと思います。
葬儀に参列した場合のマナーはもちろんのこと、参列できなかった場合についても日頃からきちんと考えておくことで、もしもの場合でも冷静に対応できるようにしておきたいですね。