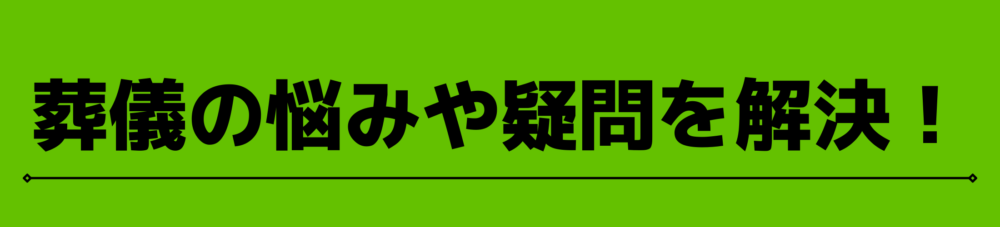お通夜や告別式の時に限って新札しかない・・・。
お札の向きもよく分からないし、新札しかない時ってどうすればいいの?
結婚式などの慶事ではピン札でないといけないということは、多くの方が知っているかと思います。
では、通夜や葬儀・告別式などに持参する御香典はどうでしょうか。
この記事でわかる事
- 葬儀やお通夜の香典でピン札がダメな理由
- お札の入れ方やピン札しかない時の対処法
- 香典袋の書き方
- 御仏前に新札は使用していいのか
- 御仏前のお札の入れ方
今回は、お通夜や葬儀・告別式や法事などの弔事の際のお札の向きや新札しかない時の対処法などを紹介していきます。
葬儀の香典でピン札がダメな理由


しわの無い綺麗なお札の方が失礼にならないと思うけど、なんでダメなの?
香典でピン札を使ってはいけない理由は以下の2つです。
- 「不幸を予期していた」
- 「あらかじめ準備していた」
香典は、線香や供花の代わりに霊前に供えるもので、故人への弔意を表すためだけではなく、葬儀などで突然の出費に対してお互いに助け合うという意味を持っているとも言われています。
そのため、御香典など弔事においてピン札を使うことは、ご法度となっているんです。
また、新たな不幸を招かないようにという願いも込めて古いお札を使用する、とも言われています。
ただ、ピン札がダメといっても破れていたり、あまりにも汚れているようなものはもちろん避けてください。
ピン札しかない時はどうするの?

訃報の時に限ってピン札しかない・・。
こんな時はどうしたらいいの?
その場合は、二つに折るなど折り目をつけると良いでしょう。
1万円札を使用する場合は難しいですが、五千円・千円札の場合はお店でくずしても良いかもしれませんね。
香典のお札向きや入れ方のマナー


香典や御仏前に入れるお札って向きに決まりはあるのかな?
- 香典袋や中包みが封筒の場合、封筒の裏側(住所や金額を書く面)にお札の表が来るように入れます。
- 封筒以外で、半紙などで包む場合は肖像画が下になるようにお札を包みます。
- 包みを開いたときに、お札の「〇〇円」が頭からきちんと読めるように向きを考えます。
どちらの場合も、複数枚入れるときは向きをそろえましょう。
上包みと中包みに分かれている香典袋の場合、香典袋の取り扱い方にも注意が必要です。
お札を入れる中包みを取り出したり、上包みに入れるときに、水引きを外してはいけません。
香典袋に折り目がついたり、水引きが曲がったりしないように気をつけましょう。
また、香典袋の裏側の重なりは、必ず「上側が下側を覆うように」たたみます。
これは、香典だけではなく弔事の場合はすべてこの重なりになります。
「不浄なものを上から下へ流す」という意味をもっています。
香典袋の書き方
香典袋は宗教によって使うものが異なってくるのですが、御仏前と書かれたものであれば、どの宗教でも使用する事ができます。
各宗教の香典袋や表書きについては、以下の記事で詳しく解説しています。
-

-
参考香典袋の書き方マナーを紹介!中袋がない時の住所は横書きでもいいの?
続きを見る
身内関係の香典の相場はどのぐらい?

身内関係の香典の相場は以下のようになっています。
- 故人との関係が兄弟の場合は3〜5万円
- 故人との関係が祖父母の場合は1〜5万円
- 故人との関係が両親の場合は3〜10万円
- 故人との関係が叔父・叔母の場合は1〜3万円
- 故人との関係が従兄弟の場合は5千円〜1万円
年齢によって金額相場は変わってくるのですが、普段のお付き合いの程度での金額を検討するようにしましょう。
また結婚して姓が変わっている場合は、配偶者との連名で香典を包むのが一般的です。
会社関係の香典の相場はどのぐらい?

会社関係での香典の金額相場は以下のようになっています。
- 故人が上司やその親族の場合は5千円〜1万円
- 故人が部下やその親族の場合は5千円〜1万円
- 故人が同僚やその親族の場合は5千円〜1万円
- 故人が取引先の場合は上司の指示に従う
会社関係というのは、関係が微妙なことも多く特に迷うことが多いようです。
また、自分が上司か、部下かという立場によっても金額が変わってきます。
会社によっては規定や慣習で決まっている場合もありますので、その場合は会社に従うようにしましょう。
-

-
参考香典を会社の連名で出す時の書き方を紹介!中袋の向きや相場についても!
続きを見る
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ピン札でも古いお札でもどちらでも良いのでは?
お札の向きもどちらでも良いのでは?
と思われる方や、今まで特に気に留めたことのなかった方もいらっしゃるかもしれません。
小さな事かもしれませんが、それらには故人や遺族に対する気遣いや弔意などの心遣いが込められているのです。
このような細やかな心配りができるのは日本人ならではですね。