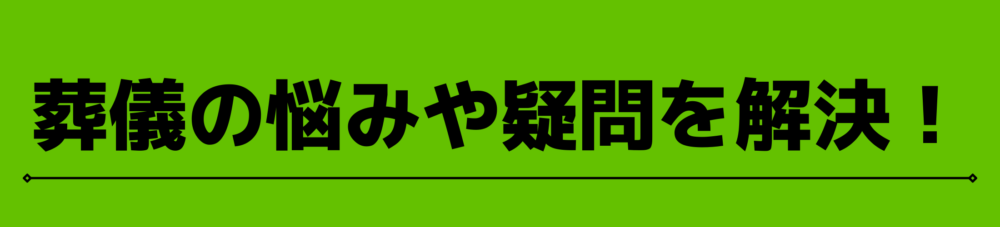「葬儀って、日程はどうやって決めればいいの?」
「大安や仏滅って、やっぱり気にした方がいいのかな…」
ご家族を亡くされたばかりで、心の整理がつかない中、
突然やってくるのが「葬儀の日程を決める」という現実です。
実際、葬儀の準備で最も多く寄せられるのが、
「いつ葬儀を行うべきか」「仏滅は避けるべきか」など、日程に関する不安や疑問。
火葬場の予約や親族のスケジュール、宗教的な都合など、
さまざまな要素が絡むため、正解がひとつではないのも難しいところです。
そこで本記事では──
-
葬儀の日程はいつ、どのように決まるのか
-
六曜(大安・仏滅)をどこまで気にするべきなのか
-
日程を決めるうえでの注意点や、避けられないときの対応方法
といったポイントを、初めて葬儀を準備する方にもわかりやすく解説していきます。
「後悔のないお別れ」にするために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
葬儀の日程はいつ決まる?基本の流れを知ろう
葬儀の日程は、「なるべく早く決めなくてはいけないもの」ではありますが、
同時に「いろいろな条件を考慮して決める必要があるもの」でもあります。
特に初めて喪主を務める方にとっては、
「いつ、誰が、どうやって決めるのか?」という点がわからず、不安に感じることが多いものです。
ここでは、葬儀日程が決まる一般的な流れを簡単にご紹介します。
訃報から葬儀までの基本的な流れ
亡くなられた直後から、葬儀まではおおむね以下のような流れで進みます。
-
ご逝去(病院・施設・自宅など)
-
葬儀社への連絡(24時間対応)
-
搬送・安置先の決定(自宅または安置施設)
-
打ち合わせ(葬儀の形式・規模・日程など)
-
火葬場・式場の空き状況を確認して日程を決定
-
関係者へ連絡、準備を開始
つまり、日程を決めるのは安置が済んだあとの早い段階で行われることがほとんどです。
葬儀までの平均日数はどのくらい?
地域や火葬場の混雑状況にもよりますが、
亡くなられてから1〜3日後に通夜、さらにその翌日に告別式というのが一般的です。
たとえば、
-
1日目:ご逝去・搬送・安置
-
2日目:打ち合わせ・火葬場・式場の予約
-
3日目:通夜
-
4日目:葬儀・告別式・火葬
ただし、火葬場が混み合っている地域では「亡くなってから5〜7日後」になるケースもあります。
また、参列者の調整や菩提寺の都合によっても前後するため、柔軟な対応が必要です。
日程は「決める」というより「調整していく」もの
葬儀の日程は、遺族の希望だけでは決められません。
-
火葬場や式場の空き状況
-
僧侶(神職)の予定
-
遠方からの親族の到着日
-
喪主自身の体調や準備状況
こうした複数の条件をすり合わせながら、現実的に無理のない日程を調整していく作業になります。
いきなり「この日でお願いします」と決めるのではなく、
信頼できる葬儀社に連絡し、空き状況を確認してもらいながら調整していくのが一般的です。
そのため、事前に葬儀社を決めておいたり、資料を取り寄せておくことが、実はとても大きな安心材料になります。
続きを見る

参考感謝のお葬式の資料請求は必要?葬儀の事前準備で後悔しないために知っておきたいこと
葬儀で六曜(大安・仏滅など)はどこまで気にすべき?
「葬儀の日程、仏滅って避けたほうがいいのかな…?」
「大安にできれば理想だけど、日が合わなくて…」
葬儀の日程を決める際、よく話題になるのが「六曜(ろくよう)」です。
特に年配の親族がいる場合や、地域の風習に敏感なご家庭では、
六曜を気にするべきかどうか、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、六曜の意味と、実際に葬儀ではどの程度重視されているのかを解説していきます。
六曜とは?それぞれの意味を簡単に解説
六曜(ろくよう)は、カレンダーに記載されている6つの運勢のような指標です。
それぞれの日に縁起の良し悪しがあり、結婚式や葬儀の際に参考にされることがあります。
| 六曜 | 意味・特徴 |
|---|---|
| 大安 | 「大いに安し」すべてに吉。お祝いごとによく選ばれる |
| 友引 | 「共に引き合う」→火葬を避ける傾向がある(友を引くため) |
| 先勝 | 午前が吉、午後は凶とされる |
| 先負 | 午前が凶、午後は吉とされる |
| 赤口 | 正午前後が吉、それ以外は凶 |
| 仏滅 | 「仏も滅するほど縁起が悪い」 → 一般的に不吉とされる |
実際のところ、六曜はどのくらい気にされている?
実は、六曜を絶対視して避けるというケースは年々減ってきています。
葬儀においては、以下のような考え方が一般的です。
-
仏滅でも葬儀は問題なく行われる
-
友引の日は、火葬を避ける地域があるが、葬儀自体は行うことがある
-
「火葬場が空いているかどうか」が実質的な日程の優先要素になる
特に都市部では、火葬場の混雑や親族のスケジュールを優先して、
六曜をあまり気にせず決めるケースが多くなっているのが現状です。
一方で、地域によっては「仏滅はなるべく避けたい」「友引はNG」という風習が根強く残っているところもあるため、
心配な場合は、事前に家族や寺院と相談しておくと安心です。
宗教的には問題なし?六曜と仏教の関係
六曜はもともと中国の暦注から来た占い的な風習で、仏教とは本来関係がありません。
つまり、仏教的に「仏滅の日に葬儀をしてはいけない」という決まりは一切ありません。
実際、多くのお寺や宗教者も「日柄よりも気持ちの方が大事」とおっしゃっています。
ご家族の中で気にされる方がいなければ、六曜にこだわらず、
現実的に無理のない日程を優先するのが一般的です。
日程を決めるときの5つのポイント【トラブルを防ぐために】
葬儀の日程を決める際は、家族の希望だけでなく、
さまざまな条件や関係者との調整が必要になります。
「この日がいい」と思っていても、実際には予定通りにいかないことも多く、
事前に押さえておくべきポイントを知らずに進めてしまうと、
あとからトラブルや後悔につながってしまうケースもあります。
ここでは、葬儀の日程を決めるときに意識しておきたい5つの重要な視点を解説します。
① 火葬場・式場の空き状況
葬儀の日程を決めるうえで、最も現実的な制約になるのが火葬場や式場の空き状況です。
特に都市部では火葬場が混み合うことも多く、
「最短でも3日後」「人気の式場は1週間先まで埋まっている」などというケースも珍しくありません。
そのため、まずは葬儀社に連絡し、
火葬場や式場の空き状況を確認したうえで候補日を絞っていくのが基本です。
② 親族や関係者のスケジュール調整
次に考慮したいのが、親族や近しい人たちの都合です。
特に喪主や故人の兄弟姉妹、遠方から来る親族がいる場合は、
「移動に時間がかかる」「宿泊が必要」などの事情を考慮する必要があります。
可能であれば、候補日を数日提示し、グループLINEや電話などで確認しておくとスムーズです。
「直前に連絡がつかない」「日程が合わない」という事態を防ぐことができます。
③ 菩提寺や僧侶の都合
仏教葬儀を行う場合は、読経をお願いする僧侶や菩提寺の予定も確認が必要です。
菩提寺のあるお宅では、通夜・葬儀ともにお寺に連絡して
「ご住職が出仕できる日程」で調整することが一般的です。
寺院によっては他の法要や儀式が入っていることもあるため、
火葬場・式場の空きと併せて、お寺の予定もできるだけ早めに確認しておくことが大切です。
④ 六曜(大安・仏滅など)を気にするかどうか
先ほど解説したとおり、六曜(仏滅や友引)をどこまで考慮するかは、
家族の考え方や地域の風習によって異なります。
特に「友引は火葬NG」という地域では、
火葬場自体が休業していることもあります。
(例:都内の多くの火葬場は友引に休業)
一方で、「気にしない」という方も増えてきており、
家族間で“どの程度考慮するか”を話し合っておくと判断がしやすくなります。
⑤ 行政手続きのスケジュール(死亡届・火葬許可など)
葬儀を行うには、死亡届の提出や火葬許可証の取得など、
市区町村の手続きが必要になります。
たとえば、死亡届は「死亡から7日以内」に提出が必要で、
提出後に交付される火葬許可証がないと火葬は行えません。
役所の開庁日や時間帯、休日を挟むかどうかなども考慮し、
できるだけ早めに提出→日程決定という流れにしておくと安心です。
葬儀社によってはこの手続きを代行してくれる場合もありますので、
日程を決める前に「どこまで任せられるか」を確認しておくと安心です。
複数の条件を調整しながら「現実的な最適解」を選ぶようにしていきましょう。
| ポイント | 意識すべきこと |
|---|---|
| 火葬場・式場の空き状況 | 優先度高。早めに確認が基本 |
| 親族・関係者のスケジュール | 来てもらいたい人の調整は要配慮 |
| 僧侶や寺院の都合 | 菩提寺がある場合は早めに連絡 |
| 六曜の考慮 | 家族間で方針を決めておくと安心 |
| 行政手続きのタイミング | 市役所の開庁時間・代行の有無も確認 |
どうしても仏滅しか空いていない…そんなときは?
「希望の日程は埋まっていて、仏滅しか空いていない」
「親族が集まれる日が仏滅しかなくて不安…」
そんな状況に直面する方は、意外と少なくありません。
特に火葬場や式場が混み合う都市部では、六曜を気にしていたらいつまでも日程が決まらないという現実もあります。
ここでは、「仏滅=避けるべき」という考え方に対して、実際の現場での捉え方と対処法をご紹介します。
仏滅=絶対に避けなければいけない、ではない
「仏滅」は「仏も滅するほど不吉な日」とされ、
一般的にはお祝い事(結婚式など)には不向きとされています。
しかし、葬儀においてはそもそも仏教とは無関係な迷信的な暦注であるため、
宗教的に「仏滅の日に葬儀をしてはいけない」という決まりは存在しません。
実際、多くのお寺や葬儀社はこう言います。
「日柄よりも“想い”の方が大切です。気にしすぎなくても大丈夫ですよ。」
仏滅でも葬儀を行うことは一般的です
最近では、仏滅であっても火葬場や式場が空いていれば、
問題なく葬儀が行われるケースがほとんどです。
また、「仏滅=予約が取りやすい日」と捉える方もおり、
結果として落ち着いた雰囲気の中で葬儀ができたという声もあります。
大切なのは、「家族や故人が納得しているかどうか」
形式や縁起にとらわれすぎず、現実的で無理のない日程を選ぶことが、結果的に良いお別れに繋がることもあります。
どうしても気になる場合は、できる対処法もある
それでも「やっぱり仏滅は気になる…」というご家族の声がある場合は、
以下のような対処を検討してみても良いでしょう。
✔お坊さんや葬儀社に「日柄について」の相談をする
多くの僧侶は六曜に対して寛容です。気にされる方にはお経での浄化や祈願を行ってくれることもあります。
✔家族と事前に“六曜への考え方”をすり合わせておく
親族によっては「絶対に仏滅はNG」と言う方もいるかもしれません。
その場合は、あらかじめ複数の候補日を相談しておくことで、後々の衝突を防ぐことができます。
✔通夜を仏滅に、告別式を翌日の大安にする など、日をまたぐ調整も
地域によっては、通夜と告別式を別日に分けることで柔軟な対応ができる場合もあります。
六曜はあくまで「参考」であり、「縛り」ではありません。
大切なのは、慌てず、無理なく、納得感を持って進められるかどうか”です。
迷ったときは、一人で抱え込まず、
早めに葬儀社に相談して、現実的な選択肢を一緒に考えてもらうことをおすすめします。
まとめ|後悔しない葬儀の日程決定のために、今できること
葬儀の日程を決める――
それは、精神的にも物理的にも大きな負担がかかるものです。
しかも多くの場合、突然その判断を迫られ、
冷静に考える余裕もないまま「決めなければならない」状況になります。
でも、だからこそ知っておいてほしいのは、
日程に正解はなく、大切なのは「その選択に納得できるかどうか」ということです。
ポイント
-
葬儀の日程は「火葬場・式場の空き」を軸に、親族・お寺の都合などを調整して決める
-
六曜(大安・仏滅など)はあくまで“参考”であり、宗教的な縛りではない
-
仏滅でも葬儀は可能。気になる場合は、相談・対処法もある
-
トラブルを防ぐには、「関係者と早めに話す」「信頼できる葬儀社に相談する」ことが大切
ここまでお読みいただきありがとうございました。