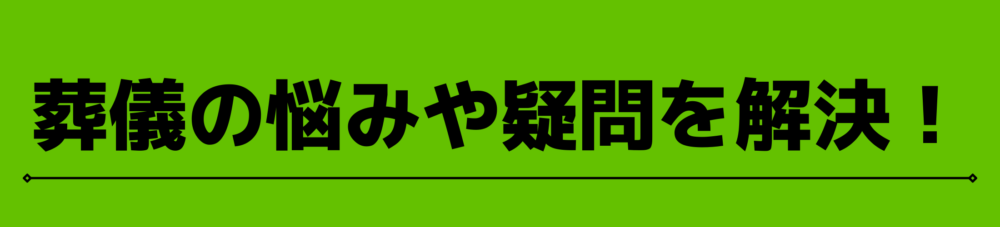「葬儀には100万円以上かかるって本当?」
「できれば費用を抑えたいけれど、失礼にならないか心配…」
そう感じている方は、あなただけではありません。
親や配偶者の葬儀を控える40〜60代の多くが、葬儀費用の高さに漠然とした不安を抱えています。
実際、葬儀は一生に何度も経験するものではないため、
「相場がわからない」
「勧められるがままに決めてしまった」
という後悔の声も少なくありません。
しかし、必要な知識とちょっとした工夫さえあれば、
無理なく、かつ失礼のない形で費用を抑えることは十分可能です。
本記事では、葬儀費用の平均や内訳を簡単に押さえた上で、
誰でも今日から実践できる6つの節約方法をわかりやすくご紹介します。
大切な人をきちんと見送るために、
そして、後悔のない選択をするために、
ぜひ最後までお読みください。
目次
葬儀費用の平均っていくら?まずは相場を知ろう
「葬儀にかかる費用って、実際どのくらいなのかよくわからない…」
そう感じている方は多いと思います。
葬儀は滅多に経験することがない分、相場感がわかりにくい上に、
明確な価格が提示されないことも多く、
「言われるがままに決めたら思ったより高かった…」という後悔の声も少なくありません。
まずは、葬儀費用の全国的な平均金額と、何にお金がかかっているのか(内訳)を知っておくことで、
「節約すべきポイント」と「きちんと支払うべきポイント」が見えてきます。
日本消費者協会の調査によると、一般的な葬儀の平均費用は以下のとおりとなっていました。
| 葬儀の種類 | 費用の目安(全国平均) |
|---|---|
| 一般葬 | 約120〜200万円 |
| 家族葬 | 約60〜100万円 |
| 直葬(火葬のみ) | 約20〜40万円 |
地域差や規模によって上下はありますが、
思っている以上に高額になるケースが多いことがわかります。
費用がかさむ理由は、「見えづらいけど積み重なる項目」が多いためです。
主な内訳はこのようになっています。
| 費用項目 | 内容例 |
|---|---|
| 葬儀基本費用 | 式場使用料、棺、遺影、祭壇、進行など |
| 飲食・返礼品 | 精進料理、引き出物(香典返し)など |
| 火葬・霊柩搬送 | 火葬場使用料、車両手配など |
| 宗教者への謝礼 | お布施や読経料(宗派によって異なる) |
| その他 | ドライアイス・安置施設・オプション装飾など |
特に見落とされがちなのが、料理や返礼品の費用、
そして「オプション」として案内される祭壇のグレードアップや会場演出です。
「よくわからないまま、葬儀社に勧められるままに決めてしまった」
「見積もりでは安く感じたのに、後から追加費用がたくさんかかった」
このようなケースは決して少なくありません。
だからこそ、まずは費用の相場と構成を理解しておくことが、賢い節約の第一歩なのです。
葬儀費用を安く抑える6つの方法
葬儀費用を左右する一番のポイントは「葬儀の規模」です。
多くの参列者を招く一般葬よりも、家族だけで静かに送る家族葬や直葬(火葬のみ)にするだけで、費用は大幅に変わります。
| 形式 | 費用の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 一般葬 | 約120〜200万円 | 親族+会社関係者など広く弔問がある場合 |
| 家族葬 | 約60〜100万円 | 親しい家族や少人数で行いたい場合 |
| 直葬 | 約20〜40万円 | 仏式にこだわらず火葬のみで済ませたい場合 |
「どんな形式が一番想いを込められるか」を考えて選ぶのが、無駄な出費を避ける第一歩です。
葬儀社を比較する(資料請求&複数見積もり)
同じ家族葬でも、葬儀社によって数十万円の差が出ることは珍しくありません。
理由は、プランに含まれる内容やオプション設定が異なるためです。
そのため、最低でも2〜3社の資料を取り寄せて、
-
何が基本料金に含まれているのか
-
追加費用は何があるのか
を見積もりの段階で確認しておくことが大切です。
続きを見る

参考【2025年最新版】主要5社の葬儀サービス徹底比較
自前で準備できるものは持ち込む(写真、位牌、骨壷など)
意外と見落とされがちですが、
-
遺影用の写真
-
位牌(白木ではない仮のもの)
-
骨壷や風呂敷
などは、既に用意されているもので代用できるケースもあります。
葬儀社によっては「持ち込み不可」とされることもあるため、
事前に確認した上で、できるだけ家にあるもので済ませるという意識を持つことが節約につながります。
返礼品・料理の数を見直す
返礼品(香典返し)や通夜・葬儀の料理は、数量の見誤りで数万円のロスが出やすい項目です。
特に返礼品は「多めに用意してしまって余った」パターンが多く、
キャンセルできないものはそのまま自己負担になってしまいます。
-
出席予定者数をできるだけ早く把握する
-
「数量変更が前日まで可能な葬儀社」を選ぶ
など、柔軟な対応ができる体制を選ぶのも節約のコツです。
会場のグレードや立地を調整する
「駅から近くて広い式場」は便利な反面、
施設使用料や設備費が高くなる傾向にあります。
会場選びでは、
-
親族が移動しやすいか
-
無理なく人数が収まる広さか
を基準に考えることで、“使い勝手はいいのに価格は抑えられる”式場を選ぶことができます。
不要なオプションを省く(例:生花祭壇、司会進行など)
「せっかくだから…」と営業で勧められたオプションが、
実はほとんど使われなかったり、不要だったりするケースも。
たとえば、
-
豪華な生花祭壇 → シンプルなプランでも十分美しく整う
-
司会進行 → 家族で進められる規模なら不要
-
エンバーミング(遺体保存処置) → 必ずしも必要ではない
「必要なもの」と「演出的なもの」の線引きを明確にすることが、無駄を省くコツです。
葬儀は安さだけを追求すると後悔することも
葬儀費用を抑えることは大切です。
しかし、「安さ」だけを優先しすぎると、本来大切にすべき部分が置き去りになってしまうこともあります。
「もっと丁寧に送りたかった」
「家族の気持ちがついていかなかった」
そんな後悔をしないために、ここでは節約の落とし穴についてお伝えしておきます。
価格だけで決めた結果、対応に不満が残ったケースも
ネットで「最安値」と紹介されていた葬儀社に依頼した結果、
-
担当者の対応が事務的だった
-
進行や段取りが不安定だった
-
相談しづらくて不信感が残った
という声が寄せられることがあります。
葬儀は、「価格」以上にスタッフとの信頼関係や、当日の安心感が大切です。
金額だけで判断せず、「どこまで寄り添ってくれるか」「説明がわかりやすいか」もあわせて見ておくと安心です。
家族・親族との関係にも影響が出る場合がある
「安さを重視しすぎて、家族や親族の気持ちが置いていかれた」
というケースも見受けられます。
たとえば、
-
遠方の親族が来る前に火葬を済ませてしまった
-
お別れの時間が短すぎて、心の整理がつかなかった
-
見送りの形式に納得できず、後味の悪さが残った
節約する際は、金額面だけでなく誰のための葬儀なのかという視点も忘れないようにしましょう。
「本当に必要なもの」はけっして削らない
たとえば、
-
遺影写真は故人の面影を残す大切な記録
-
祭壇や装飾は心の区切りをつけるための空間
-
僧侶の読経や挨拶は、心を整える時間
こうした「金額では測れない価値」を削ってしまうと、後から喪失感が増してしまうこともあります。
節約をする際は、「省けるもの」と「残すべきもの」をしっかり区別し、
納得して選んだ結果の節約であることが、後悔のない葬儀への近道です。
大切なのは、「安さのために妥協する」ことではなく、
「自分たちにとって本当に必要なものを選び取ること」
そのためには、信頼できる葬儀社に相談しながら、
しっかりと説明を受けて判断する姿勢が何よりも大切です。
費用と納得感を両立したいなら、まずは資料請求を
「なるべく安く、でもちゃんと納得できる葬儀にしたい」
──それは、多くの方が抱える本音です。
とはいえ、インターネット上の情報や口コミだけでは、
どの葬儀社が自分たちに合っているのかを見極めるのは難しいもの。
そんなときに役立つのが、無料の資料請求です。
葬儀の費用は、ホームページに書かれたプラン料金だけでは判断できません。
資料を取り寄せることで、以下のような重要な情報が手に入ります。
| 資料でわかること | 具体例 |
|---|---|
| 各プランに何が含まれているか | 「基本料金に含まれるもの/オプション」の違い |
| 実際の総額はいくらくらいになるのか | 人数や地域に応じた目安総額 |
| 火葬場・式場の手配がどのくらい柔軟にできるか | 日程調整や立地条件への対応力 |
| 追加料金が発生しやすいタイミングと項目 | 「棺の種類変更」「安置日数延長」などの注意点 |
「思ったより安かった」
「逆に、このオプションは必要だとわかった」
そんな気づきが得られるのも、紙ベースの資料だからこそ比較しやすいメリットです。
複数社を比較すれば、納得感のある選択ができる
1社だけでなく、2〜3社の資料を見比べてみることで、自分に合った価格帯とサービスのバランスが自然と見えてきます。
-
A社:安いが内容がシンプルすぎる
-
B社:丁寧なサポートが魅力だが費用は高め
-
C社:費用とサービスのバランスが良く、説明もわかりやすい
こうした比較の中で生まれる納得感こそが、
後悔しない葬儀を選ぶための最大のカギです。
資料には、電話相談やLINE対応、事前見積もりの受付など、
その葬儀社の対応姿勢がにじみ出る情報が多数含まれています。
「この会社なら、聞きたいことを気軽に相談できそう」
そう思える会社に出会えたときこそが、準備への一歩目です。
続きを見る

参考【2025年最新版】主要5社の葬儀サービス徹底比較
まとめ|無理のない節約で、後悔しないお見送りを
葬儀は、「一度きりのお別れ」
だからこそ、費用だけでは測れない心の納得感がとても大切です。
とはいえ、予算に限りがある中で「できるだけ無理なく、でもきちんと送りたい」と思うのは当然のこと。
今回ご紹介した6つの節約方法は、その想いを叶えるための現実的でやさしい工夫ばかりです。
今回紹介した「葬儀費用を抑える6つの方法」
-
葬儀の形式を見直す(一般葬 → 家族葬・直葬)
-
複数の葬儀社で資料請求・見積もりを比較する
-
自分で準備できるものを持ち込む
-
返礼品・料理の数量を最小限に調整する
-
会場のグレードや立地を見直す
-
不要なオプションはきちんと断る
節約とは、「本当に必要なものだけを選び取ること」。
金額を抑えるだけでなく、想いを込められるかどうかも、選ぶうえで大切にしたい視点です。
そのためには、「どこで、何に、いくらかかるのか」を事前に把握することが欠かせません。
迷ったときは、まず資料請求で情報を集めるところから始めてみてください。