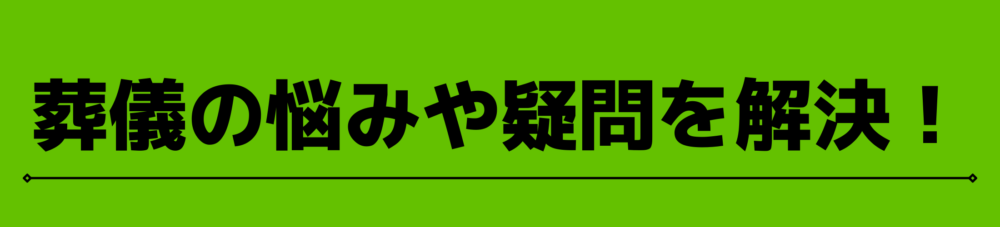葬儀の準備を進める中で、ふと悩むのが「遠方から来る親族の交通費や宿泊費って、こちらが負担すべき?」という点。
飛行機や新幹線で数時間かけて来る人もいれば、宿泊が必要な人もいる。
喪主としては丁寧にお迎えしたい一方で、予算のことも考えると簡単には決められない…という声も多くあります。
実はこの問題、明確なルールがあるわけではなく、地域性や家族の関係性によって判断が異なるものです。
そのため「正しい対応」がわからず、あとでトラブルになるケースも少なくありません。
この記事では、以下のポイントをわかりやすく解説していきます。
ポイント
-
交通費・宿泊費を「誰が」「どこまで」負担するのが一般的か
-
実際の判断ポイントや対応例
-
支払う場合の相場や渡し方のマナー
-
家族間で揉めないための事前確認の工夫
失礼のない対応をしながら、無理のない範囲で気持ちよく送り出すためのヒントをお伝えします。
目次
葬儀で親族の交通費・宿泊費は誰が負担するのが一般的?
葬儀の場において、遠方から来る親族の交通費や宿泊費を誰が負担するかに関して、明確な決まりや法律はありません。
しかし、地域や家族ごとの慣習によって「それとなく決まっている」ことが多く、悩みの種になりやすい部分です。
では、一般的な傾向としてはどうなっているのでしょうか?
基本的には「自己負担」が多い
近年では、交通費・宿泊費は本人が負担するのが一般的という考え方が主流です。
特に都市部ではこの傾向が強く、「香典で気持ちはいただいている」として交通費までは出さないケースが多くなっています。
ただしこれはあくまで近年の傾向であって、
昔ながらの家柄や、地方の風習が残る地域では「施主側が一部または全額負担する」のが当然という認識もあります。
費用を出すかどうかは、関係性や距離によって変わる
たとえば以下のような条件によって、対応は変わってくることがよくあります。
-
故人と親しかった人(兄弟姉妹、親など)にだけ費用を出す
-
飛行機・長距離移動が必要な親族には宿泊費だけでも用意する
-
高齢で経済的に負担が大きそうな親族には気遣いとして包む
つまり「全員に同じ対応をする必要はないが、配慮が感じられる対応かどうか」が大切なポイントになります。
家族葬では「お招きした側」として負担するケースも
家族葬など、人数を絞って行う場合は、
「お越しいただくことをお願いした」側として、交通費や宿泊費を施主側が負担するケースも増えています。
たとえば、数人の親族だけを招く形式であれば、
「遠方からわざわざ来てもらったお礼に」という意味を込めて、交通費の一部やホテル代をお渡しすることも丁寧な対応です。
費用を出すかどうかに正解はありません。
ただ「出す/出さない」の方針を明確にした上で、早めに家族内で共有し、相手に丁寧に伝えることが、後のトラブル防止にもなります。
遠方から来る親族の交通費・宿泊費対応|判断のポイントと例
交通費や宿泊費の負担については、“家としてどうするか”の方針を決めることが大切です。
ただ、その判断は一概に「全額出す or 出さない」と決めづらいもの。
ここでは、対応を決める際に参考になる判断軸と代表的な3つの対応例を解説します。
判断のポイント①:故人との関係性
-
故人の兄弟姉妹・実の親・子どもなど、関係が深い親族ほど配慮されることが多いです。
-
「そこまでの関係ではない」場合は、自己負担でも失礼にはなりません。
たとえば、
・兄が飛行機で来る → 往復の航空券をこちらで手配・負担
・いとこが来る → 自己負担でお願いしつつ、お礼の品や心付けを用意
判断のポイント②:移動距離・交通手段
-
飛行機、新幹線、長距離バスなどの利用は負担が大きいため、費用の一部を出すケースも増えています。
-
逆に、片道1〜2時間程度であれば、自己負担が一般的です。
たとえば、
・関西→東京など遠方の場合 → 宿泊手配+片道だけでも交通費を負担
・都内近郊→東京 → 自己負担が基本
判断のポイント③:年齢や経済状況
高齢の親族や、学生・無職の方など経済的に負担が重そうな方には、気遣いとして交通費を用意することも配慮のひとつです。
たとえば、
・80代の伯母 → 「無理せず来てね」と交通費+宿泊費を準備
・学生の甥 → 交通費のみ支給し、宿泊は家で受け入れ
よくある3つの対応パターンは以下の通りです。
| 対応パターン | メリット・注意点 |
|---|---|
| ① 全員自己負担 | もっとも一般的で明朗。ただし年配者や近親者にはやや冷たく感じられることも |
| ② 宿泊だけ施主側が手配 | 負担を抑えつつ気遣いを見せられるバランス型。ビジネスホテルなどをまとめて予約 |
| ③ 交通費+宿泊費を支給 | 人数が少ない家族葬などにおすすめ。感謝を込めて丁寧なお迎えができる |
必ずしも全員一律でなくても大丈夫です。
関係性や状況に応じて、一部の親族にだけ費用を出すこともマナー違反ではありません。
ただし「あの人には出したのに、自分にはなかった」と不満が出ないよう、
事前に家族で方針をすり合わせておき、できるだけ早めに説明しておくことが大切です。
費用を出す場合の相場・包み方・伝え方マナー
「費用は出すことに決めたけれど、いくら包めばいいのか分からない」
「渡し方やタイミングにマナーってあるの?」
こんな疑問を抱く方はとても多くいらっしゃいます。
ここでは、金額の目安や渡し方、言葉づかいなど、葬儀の場にふさわしい対応方法を詳しくご紹介します。
交通費・宿泊費の相場目安
目安は、距離や交通手段に応じて以下のように考えるのが一般的です。
| 交通手段 | 支給額の目安 |
|---|---|
| 新幹線(往復) | 1万5,000円〜3万円程度 |
| 飛行機 | 2万〜5万円前後(距離により) |
| 高速バス | 実費分(5,000〜1万円程度) |
| 宿泊費(1泊) | ビジネスホテルで5,000〜1万円前後 |
※すべて「実費」ではなく「気持ち」としての一部負担と考えるケースが多いです。
包むときのマナーと封筒の選び方
費用を現金で渡す際は、以下のようなマナーを意識しましょう。
✔ 封筒は「白封筒」または「無地ののし袋」
-
表書きは「御車代」「御宿泊御礼」など
-
水引は不要(あっても黒白の結び切りで)
✔ 新札ではなく、折り目をつけたお札が好ましい
-
「慶事ではない」ため、新札を避けるのが一般的なマナーです。
渡すタイミングと声かけの例
通夜や告別式の受付後・帰るタイミングなど、相手が落ち着いたタイミングで、
さりげなくお渡しするのが理想です。
✔ 声かけ例:
-
「遠くからお越しいただきありがとうございます。ご負担もあったかと思いますので、こちらを…」
-
「ほんの気持ちですが、お足代としてお受け取りいただければ幸いです」
※形式ばった表現よりも、感謝の気持ちを込めた自然な言葉が一番です。
領収書は必要?記録はどう残す?
基本的に、親族間でのやり取りでは領収書は不要です。
ただし、後から家族内で「誰にどれだけ渡したか」を共有するために、
-
金額の控えをメモしておく
-
渡した相手・金額・用途を簡単にまとめる
といった記録を残しておくとトラブル防止になります。
たとえ金額が少なかったとしても、
「ありがとう」という気持ちが伝われば、それだけで十分に温かなおもてなしになります。
逆に、高額であっても形式的で無言のままだと、誤解や距離感が生まれてしまうことも。
心を込めた対応で、故人に代わって「ありがとう」を伝えること。
それが、喪主として最も大切な姿勢かもしれません。
親族間で揉めないために|事前に確認・共有しておくべきこと
交通費や宿泊費に関しては、対応そのものよりも、
「誰に・何を・どう伝えるか」を曖昧にしてしまうことでトラブルになるケースが多くあります。
とくに「自分には出なかったのに、あの人には出ていた」といった不公平感は、
葬儀後の関係にも尾を引く原因になりかねません。
そうならないために、事前の確認と共有がとても大切です。
事前に「誰に出すか/出さないか」の基準を決めておく
まずは、以下のような観点から、家族内でルールを明確にしておくのが理想です。
-
血縁の近さで線引きする(例:2親等までには出す)
-
距離・年齢で決める(例:遠方+高齢の方には交通費を)
-
家族葬で“招いた人”には宿泊手配をする
すべてに対応するのは難しいため「ここまでにする」というラインをあらかじめ決めることでブレを防げます。
家族間で共有しておくべき情報リストを以下の表にまとめました。
| 共有すべき項目 | 内容例 |
|---|---|
| 誰に費用を出すか | 「父の妹には宿泊代を出す」「いとこは自己負担」など明確に記録する |
| 実際にかかる金額の目安 | 飛行機代・ホテル代・封筒の準備など、予算を把握する |
| 誰が調整・連絡するか | 喪主だけで抱えず、家族内で役割を分担する |
こうした情報を家族間で共有しておくだけで、「言った/聞いてない」のすれ違いが激減します。
伝え方のポイント|角が立たない一言例
連絡はなるべく早く、LINE・メール・電話などで事前に伝えることが望ましいです。
以下は、そのまま使える角の立たない一言例です。
参考
出さない場合の文例:
「大変恐縮ですが、交通費と宿泊費につきましては、皆さまにご負担をお願いしております。どうぞご了承くださいませ。」
参考
出す場合の文例:
「遠方からのご移動、本当にありがとうございます。ささやかですが宿泊費はこちらでご用意させていただきます。」
どちらの場合も、感謝を先に伝えることがポイントです。
万が一のトラブル回避にも「事前相談」が有効
もし迷いや不安がある場合は、
葬儀社に相談することで「一般的な対応例」や「丸く収まる提案」をしてもらえることがあります。
特に経験豊富な葬儀社は、こうしたお金の話を角を立てずに伝えるコツにも慣れているので、ぜひ活用してみましょう。
まとめ|無理のない範囲で、気持ちよく迎える工夫を
葬儀の場での交通費や宿泊費の対応は、
金額や形式だけでなく、「どう気持ちを伝えるか」「どれだけ配慮できるか」が問われる場面でもあります。
大切なのは、こうすべきに縛られることではなく、無理のない範囲で誠意を持って対応すること。
たとえ全額を出せなかったとしても、
「遠くから来てくれてありがとう」という気持ちが伝わるだけで、相手にとっては十分なもてなしになるのです。
記事のまとめ
-
遠方から来る親族の費用は「自己負担」が基本だが、状況に応じて柔軟な対応を
-
対応を決める際は、「距離・関係性・年齢・経済状況」などを総合的に判断
-
渡す場合は、適切な金額・封筒・言葉づかいで丁寧に
-
不公平感が出ないよう、事前に家族間で方針を共有しておくと安心
-
困ったときは葬儀社に相談を。第三者の視点が解決のヒントになることも
葬儀は、故人を見送るだけでなく、
残された人たちの気持ちをつなぐ場でもあります。
お金の問題に神経質になりすぎず、
「ありがとう」「来てくれて嬉しい」という言葉と共に、
心地よい距離感で迎えることが何より大切です。