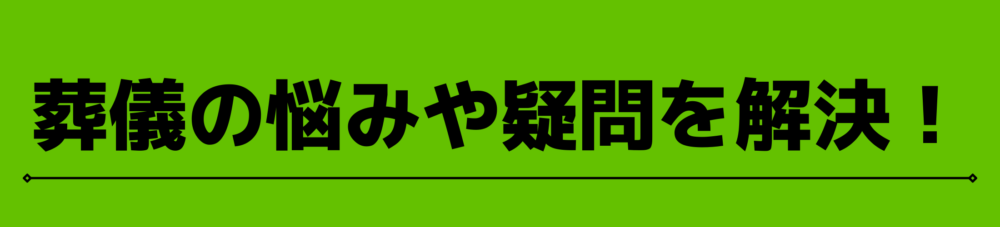家族葬の平均費用ってどれぐらいなんだろう?
こんな疑問に答えていきたいと思います。
この記事でわかる事
- 家族葬の平均費用
- 家族葬の内訳
- 家族葬の費用を安く抑える方法
家族葬は一般葬に比べると費用を抑えることができますが、その費用も葬儀社によって変わってきます。
また、一般葬と違って香典を辞退するケースが多いので、香典で葬儀費用の補填をするのも難しくなってきます。
そこで今回は、家族葬の平均費用や安く抑える方法について解説していきたいと思います。
家族葬の平均費用

家族葬の平均費用は参列する人数にもよりますが、50万円~80万円ほどで執り行うことができます。
100万円近い平均費用も書かれていたりしますが、基本は50万円〜80万円で収まります。
日本消費者協会などが「葬儀アンケート」で葬儀の平均費用を出すことがありますが、葬儀アンケートの結果は、アンケートのサンプルが少ない上に調べてみたらすぐに分かるほど高額になっています。
ちなみにですが、2017年の葬儀アンケートに基づく葬儀の平均費用は189万円となっていましたが、どう考えても今の葬儀でこの金額になることはありません。
おはようございます。
今回初めて家族の通夜と葬式、医療費などを含めてかかった費用は凡そ80万円でした。家族葬でこれくらい。
うちの場合は10日間、個室入院で治療費込みで8万円弱。
住職さんの費用19万(戒名代除く)
火葬費4万(帰りに現金払い)
業者に頼んだ通夜と葬式の費用44万円弱。→— 上の森シハ (@shiha510) June 29, 2018
葬儀は、葬儀担当者との打ち合わせで必要なオプションを追加することで費用が加算されていきます。
よっぽど悪徳な葬儀社にあたらない限り、必要のないオプションを追加されて高額になる事はありません。
家族葬の内訳と内訳以外にかかる費用

家族葬の内訳は以下の表の通りです。
今回は偏りを防ぐために、葬儀社3社を比較しています。
|
家族葬プランに含まれるオプション |
葬儀社A |
葬儀社B |
葬儀社C |
|
費用 |
407,000円 |
639,970円 |
438,900円 |
|
寝台車 |
○ |
○ |
○ |
|
預かり安置 |
4日間 |
4日間 |
|
|
ドライアイス |
4日分 |
2日分 |
4日分 |
|
枕飾り一式 |
○ |
○ |
○ |
|
手続き代行 |
○ |
○ |
○ |
|
棺一式 |
○ |
○ |
○ |
|
納棺 |
○ |
○ |
|
|
仏衣一式 |
○ |
○ |
○ |
|
式場料金 |
50,000円分 |
50,000円分 |
100,000円分 |
|
生花祭壇 |
○ |
○ |
○ |
|
遺影写真 |
○ |
○ |
○ |
|
焼香用具 |
○ |
○ |
○ |
|
仏具一式 |
○ |
○ |
○ |
|
運営スタッフ |
○ |
○ |
○ |
|
付き添い安置 |
○ |
○ |
|
|
受付セット |
○ |
○ |
○ |
|
会葬令状 |
30枚 |
60枚 |
|
|
お花入れ |
○ |
||
|
遺影花飾り |
○ |
||
|
収骨 |
○ |
○ |
○ |
|
骨壷・骨箱・骨覆 |
○ |
○ |
○ |
|
後飾り祭壇 |
○ |
○ |
このように各葬儀社でプランに含まれるオプションも費用も異なってきます。
なので、各葬儀社の費用の比較はしっかりと行いましょう。
家族葬の費用があまりにも安すぎる葬儀社は、必要のないオプションをどんどん付けていこうとする事があるので避けましょう。
宗教関係者への支払い
仏式の場合は僧侶、キリスト教の場合は教会への献金や神父、牧師へのお礼などがあります。
宗教関係者への支払いも地域ごとに異なってきます。
- 北海道や東北地方だと平均15万円。
- 関東や近畿地方だと平均20万円。
- 中国、四国、九州地方だと平均15万円。
接待飲食代
家族葬の場合は、通夜振る舞いや精進料理を省くことも多いので、通夜振る舞いや精進料理が必要だとその分、費用はかかります。
香典返し
家族葬は基本的に香典や供花を辞退することがほとんどなので、香典返しなどの必要もあまりありません。
家族葬の費用を安く抑える3つの方法

家族葬の費用を安く抑える上で大切なのは以下の3つ。
家族葬の費用を抑える3つの方法
- 葬儀社の比較
- 葬儀社の会員になる
- 不要なオプションは断る
1つずつ解説していきます。
葬儀社の比較
全国の葬儀社の数は現在、2163社あると言われています。
お住まいの地域に葬儀社が10社あるなら10社全てから見積もりはもらうべきです。
1社2社だとそこまで料金に偏りは見られないですが、これが10社になると明らかに費用の違いが出てきます。
安すぎる葬儀社は注意しつつ、平均的な料金の葬儀社をピックアップしていきましょう。
葬儀社の会員になる
現在、多くの葬儀社で会員制度が導入されています。
経過年数で通常の葬儀費用から割引されたり、エンディングノートをプレゼントするなどの特典が受けられるようになります。
生前にご自身の葬儀の相談をする方も増えているので、葬儀の相談をしつつ、会員になって特典を受けるのもいいでしょう。
葬儀の生前見積もりメリットについて以下の記事で解説してます。
不要なオプションは断る
家族葬のみならず、どのような葬儀形式でも不要なプランを削る事は大切です。
悪徳な葬儀社は言葉巧みに不要なオプションを付けようとしてきます。

- 皆さんこのオプションもご利用されています。
- きっと故人様も喜んでくれると思います。
など寄り添うフリをしつつ、スッとオプションの追加を提案してくるので、不要だと思ったオプションについては断る勇気も必要です。
全ての葬儀社がそういう風な悪徳葬儀社ではありませんが、葬儀社との打ち合わせは絶対に1人でしない事が鉄則です。
【まとめ】家族葬の費用の平均金額はいくら?安く抑える方法についても
急な葬儀になると、一般葬との費用の差があるとはいえ費用が抑えられるものも抑えきれず、高額な請求に驚くことになります。
解説させて頂いた家族葬の費用を抑える3つの方法も視野に入れつつ、後悔しない葬儀社選びをしましょう。