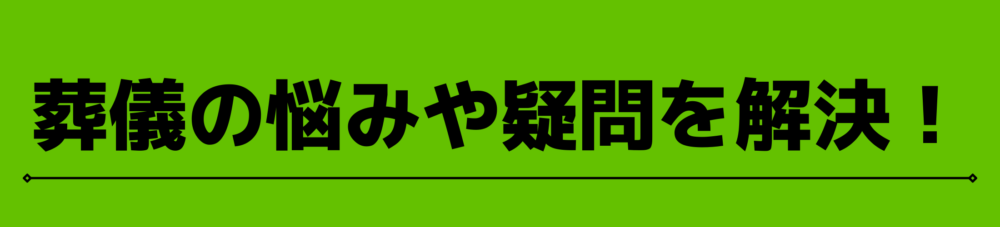葬儀の場面で「供物(くもつ)」を贈ることになったとき、こんなふうに迷った経験はありませんか?
-
食べ物やお花、どれが適切なの?
-
宗教によって違うって聞いたけど、何に気をつければいい?
-
渡し方やタイミング、相場ってどうなってるの?
供物は、故人を悼み、感謝と哀悼の気持ちを形として表す大切な手段です。
けれど、宗教や地域によってマナーや慣習が異なるため「何をどう選べばいいのか」がわかりづらいのも事実です。
実際、
「間違った物を贈ってしまった」
「失礼にならないか不安だった」
という声も少なくありません。
そこで本記事では、
-
供物とはそもそも何なのか
-
種類と特徴、宗派別の選び方
-
渡し方や配送のマナー、金額の相場まで
葬儀における供物の基本を、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
「形式だけで終わらせたくない」「失礼のない対応がしたい」――そんなあなたの参考になれば幸いです。
供物とは?
葬儀の際に贈られる「供物(くもつ)」とは、故人に対する供養の気持ちを形にした贈り物のことを指します。
一般的には、果物や缶詰、飲み物などの食品類、お線香やロウソクなどが選ばれますが、その背景には単なる手土産ではない、深い意味と敬意の表現が込められています
供物は、故人を弔い、その冥福を祈る気持ちを「物」という形に託して捧げる行為です。
それと同時に、残されたご遺族に対して、
「あなたを思っています」
「お力落としのないように」
といった思いやりや慰めの気持ちも含まれています。
特に日本の葬儀文化においては、形式的でありながらも「心のこもった行動」が重視されるため、
供物はまさに心を届ける手段として大切に受け取られます。
供物には以下のような役割があります。
-
故人への哀悼と祈り:「安らかにお眠りください」「ご冥福をお祈りします」といった祈りの形
-
ご遺族への配慮と支え:「ひとりじゃない」「お気持ちを汲んでいます」という優しさの表現
-
宗教的意味合い:仏教では功徳(くどく)を積む行為とされ、キリスト教や神道でも形式の異なる供え物が存在する
[/st-mybox
供物と供花の違いとは?
供物と似た言葉に「供花(きょうか)」があります。
どちらも供えるものですが、その内容と目的には違いがあります。
| 比較項目 | 供物(くもつ) | 供花(きょうか) |
|---|---|---|
| 内容 | 食べ物・飲み物・線香・ロウソクなど | 生花、花環、アレンジメントなど |
| 見た目 | 祭壇周辺に置かれることが多い | 会場正面・遺影の横などに並べられる |
| 目的 | 故人の冥福を祈る + 遺族への慰め | 故人への花による供養・空間演出 |
| 渡し方 | 会場に持参/斎場に配送/現金で代用 | 事前手配が基本(斎場・葬儀社宛) |
供物は、より「実用的な供養」として選ばれる傾向があり、
供花は「視覚的な供養」や「場の格式を保つ演出」としての意味合いが強くなります。
地域や宗派によっても意味が変わる
供物の内容や贈り方は、地域性や宗教・宗派の影響を受けることもあります。
たとえば、
-
仏教(浄土真宗・曹洞宗など):供物・供花どちらもよく使われる
-
神道:お線香ではなく榊(さかき)やお酒などが供えられる
-
キリスト教:供花のみが一般的で、供物や香典を避けることも
そのため、「一般的にはこう」という知識だけで動かず、故人やご遺族の宗教・地域の慣習を確認することが何より大切です。
どれだけ正しい形式を選んだとしても、そこに気持ちがこもっていなければ供物とは呼べません。
供物の意味とは、形式的な贈り物ではなく、
「この人を大切に思っている」
「ご家族の悲しみに寄り添いたい」
そんな想いの表れです。
このあと解説する【供物の種類】や【選び方】を参考に、形式にとらわれすぎず、
あなたなりの“敬意”を伝える手段として、最適な供物を選んでいただければと思います。
供物の主な種類と特徴
葬儀で贈られる供物には、さまざまな種類があります。
「何を選べばいいかわからない」というのは、決して珍しいことではありません。
故人への想いを形にしたい気持ちはあっても、宗教的なマナーや地域の慣習が絡むと、選ぶ際にどうしても迷いが出てしまうものです。
供物には、果物や乾物、缶詰などの食品をはじめ、飲み物の詰め合わせや、お線香・ろうそくといった宗教的な品、さらには供物の代わりに現金を包む「御供料」など、用途や状況に応じたバリエーションがあります。
それぞれの供物には、「なぜそれが選ばれるのか」という理由や意味があります。
また、贈る側の立場(親族・友人・会社関係など)によっても、ふさわしい品の傾向は異なります。
この章では、代表的な供物の種類を一つずつご紹介しながら、
それぞれの特徴・選ばれる背景・注意点なども合わせて解説していきます。
「形式だけでなく、気持ちをきちんと届けたい」
そんなあなたの想いが、供物を通じて正しく伝わるよう、ぜひ参考にしてみてください。
① 食品(果物・乾物・缶詰など)
葬儀でよく選ばれる定番の供物のひとつが、食品類です。
中でも果物や缶詰、乾物などは「保存がきく」「見た目が整う」「宗派を問わず使いやすい」ため、幅広く用いられています。
特に人気が高いのは以下のようなもの。
-
果物かご(盛り籠):色合いが美しく、格式ある印象。地域によっては定番
-
缶詰セット:日持ちしやすく実用的。特に関東では多く選ばれる
-
乾物詰め合わせ:昆布や椎茸など、昔から「縁起が良い」とされる食材を使用
ポイント
火葬後、供物の一部は遺族に引き取られる場合もあるため、後に使いやすい食品を選ぶのが好印象です。
② 飲料(ジュース・お茶・ビールなど)
次に多いのが飲料の詰め合わせです。特にジュースやお茶のセットは、年齢や宗教を問わず贈りやすい供物として知られています。
以下のような組み合わせが一般的です。
-
緑茶・麦茶の詰め合わせ:落ち着いた印象で仏式でも無難
-
100%ジュースセット:果物の供物と組み合わせやすい
-
ビール・酒類:故人が好きだった場合に贈られることもあるが、宗教や地域によっては避けた方が無難
注意ポイント
アルコール類は神道・キリスト教式や一部仏教宗派ではNGとされることもあります。迷ったら事前確認を
③ お線香・ろうそくセット
宗教的な意味合いが強く、どの仏教宗派でも使用されるのがお線香やろうそくの供物です。
「香りで故人を浄化する」
「魂を導く」
とされ、形としても非常に格式のある贈り物とされています。
贈答用のセットも多く、パッケージも落ち着いたものが多いため、
-
「何を贈ればいいかわからない」
-
「あまり関係が深くないが、心だけでも届けたい」
という場合にも選びやすい供物です。
参考
のし紙の表書きは「御供」や「御仏前」が基本ですが、宗派によっては「御霊前」となることもあります。
④ 現金(供物料・御供料)
最近では、供物の代わりに現金で供物料を渡すケースも増えています。
「香典+供物を同時に用意するのは難しい」
「遠方からで品物が贈りにくい」
といった場合に便利な方法です。
この場合は、封筒に現金を包み、表書きとして以下のように記します。
-
仏式の場合:「御供」「御供物料」「御仏前」など
-
神式:「御玉串料」「御神前」など
-
キリスト教:「献花料」など
香典と同じく、不祝儀袋を使用し、新札は避ける・名前は楷書で書くなどの基本マナーを守ることが大切です。
注意ポイント
供物料は「香典とは別に包む」のが一般的です。ひとつの封筒にまとめることは避けましょう。
このように、供物にはさまざまな形があり、それぞれに意味や背景があります。
次の章では、贈る側として知っておきたい「選び方のポイント」について詳しく解説していきます。
供物の選び方
供物にはさまざまな種類がありますが、「どれを選べばよいのか」は状況や立場によって異なります。
特に初めて葬儀に供物を贈るという方にとっては「何が適切で、何が失礼にあたるのか」がわからず不安になってしまうこともあるでしょう。
また、宗教や地域の風習、そして故人やご遺族との関係性によっても、選ぶべき供物は微妙に変わってきます。
このセクションでは、そんな迷いを持つ方のために、供物を選ぶ際にチェックしておきたい3つの観点をご紹介します。
宗教・宗派に合ったものを選ぶ
葬儀では、宗教や宗派ごとに考え方やしきたりが異なります。
そのため、供物も「どの宗教に属する葬儀か」によって、ふさわしい内容が変わります。
たとえば、
-
仏教(浄土宗・曹洞宗・日蓮宗など)
→ 果物・乾物・お茶・お線香など、幅広く対応可。御供と記載したのし紙が一般的 -
神道
→ 榊(さかき)や酒、白い紙包みに包んだ食品など。表書きは「御神前」 -
キリスト教(カトリック/プロテスタント)
→ 食品はあまり用いられず、供花のみが基本。表書きは「お花料」「献花料」など
特にキリスト教式では、供物自体を辞退する場合もあるため、迷ったら葬儀社やご遺族に確認を取るのが安心です。
地域の風習に合わせる
供物の内容や贈り方には、地域ごとの特徴も色濃く現れます。
たとえば、
-
関西・中国地方では「盛り籠(果物)」が定番
-
関東では缶詰や乾物の詰め合わせが多く選ばれる
-
東北や九州では、茶や砂糖のセットが好まれることも
また、一部の地域では「供物は近親者のみ」とされることもあるため、
その地域特有の文化や慣習をリサーチしておくことが、失礼を避ける第一歩となります。
故人の好物や人柄に配慮する
最近では、形式よりも「故人らしさ」や「個性」を尊重した供物選びも増えています。
たとえば、
-
故人が甘いものが好きだった → 和菓子やフルーツを
-
お茶好きだった → 高級茶葉のセットを
-
優しい方だった → 淡い色合いの供花を選ぶなど
こうした配慮は、ご遺族にとっても「ちゃんと故人のことを覚えていてくれたんだな」という慰めになります。
ただし、生ものやにおいの強いもの、日持ちしないものは避けるのがマナー。
思いを込めつつも、葬儀の場にふさわしい品を選ぶことが大切です。
このように、宗教・地域・故人への思いという3つの観点を意識することで、
「かたちだけでない、気持ちのこもった供物選び」ができるようになります。
次の章では、供物の渡し方・贈り方のマナーについて、具体的な流れと注意点を解説していきます。
供物の渡し方・贈り方のマナー
供物は「贈ること」自体も大切ですが、どのように贈るか、いつ渡すか、誰に渡すかも重要なポイントです。
せっかく気持ちを込めて準備しても、渡し方にマナー違反があると、ご遺族に気を遣わせたり、失礼な印象を与えてしまうこともあります。
この章では、供物を持参する場合と、あらかじめ手配して送る場合の2パターンに分けて、基本的なマナーと注意点を解説します。
手渡しする場合(会場で供える)
葬儀に参列し、供物を持参して直接渡す場合は、以下の流れが基本です。
参考
▶ 1. 受付で「供物をお持ちしました」と一言添える
ご遺族または受付係に供物を渡す際は、
「御供物をお持ちしました。どうぞお納めください」など、簡潔で丁寧な言葉を添えて手渡しします。
▶ 2. のし紙をつけておく
表書きは宗派により異なりますが、仏教であれば「御供」「御仏前」、神道なら「御神前」などが基本。
名前はフルネームで楷書、連名の場合は関係性が分かるように。
▶ 3. 手渡しできない場合は係員へ預ける
斎場が広い場合や受付が混み合っている場合は、葬儀スタッフに声をかけて供物を預けるのも失礼にはあたりません。
ポイント
食品類を持参する場合は、包装が清潔で丁寧なものを選びましょう。
香典と供物を一緒に渡す場合は、袋や紙袋を分けておくのがスマートです。
葬儀前に配送する場合(斎場や葬儀社宛)
直接持参できない場合や、あらかじめ供物を手配しておきたい場合は、斎場や葬儀社へ配送する方法があります。
参考
▶ 1. 必ず“事前に確認”する
まずは、喪主や遺族、または葬儀社に「供物を贈っても良いか」確認を取りましょう。
最近では、「供物・供花は辞退」とする葬儀も増えているため、一方的に送るのはマナー違反になることも。
▶ 2. 宛名の書き方・送り状の工夫
配送時には、以下の内容を送り状に明記しましょう:
-
斎場名・斎場の住所
-
故人の名前(フルネーム)
-
葬儀の日時(通夜・告別式など)
-
喪主またはご遺族の名前(可能であれば)
注意ポイント
配送タイミングは、前日~2日前が理想です。当日午前着などは避け、余裕を持って手配しましょう。
供物の表書きと包装マナー
供物には、のし紙(掛紙)をつけるのが一般的です。選ぶときのマナーを簡単にご紹介します。
-
表書き(上段):
仏式→「御供」「御仏前」
神式→「御神前」
キリスト教→「献花料」など -
名入れ(下段):贈り主のフルネームを楷書で
-
水引:黒白/双銀/黄白など、地域によって異なるが、基本は結び切りのスタイル
包装については、控えめで清潔感のあるものを選び、必要に応じて風呂敷や紙袋に入れて持参するのが望ましいです。
供物の相場は?誰がどれくらい出すの?
供物を選ぶ際、もうひとつ気になるのが「金額の相場」。
あまりに高価すぎても気を遣わせてしまいますし、逆に安すぎると失礼に感じられることもあります。
ここでは、供物の一般的な金額感と、贈る側の立場別にみた相場の目安をわかりやすくまとめました。
親族の場合(5,000〜10,000円程度)
故人の親族として供物を贈る場合、5,000円〜10,000円程度がひとつの目安です。
-
子や孫など近親者:10,000円程度
-
甥姪・いとこなどやや遠い親族:5,000円〜7,000円程度
ただし、親族内で「供物はまとめて手配する」などの取り決めがある場合もあるため、
喪主や他の親族と事前に連絡を取り、重複や不統一がないように調整するのが望ましいです。
友人・知人・ご近所の場合(3,000〜5,000円程度)
故人と生前親しかった友人や、ご近所の方などが供物を贈る場合は、3,000円〜5,000円程度が一般的です。
-
長年の友人や恩人:5,000円程度
-
近所づきあいや知人関係:3,000円前後
供花を贈る場合よりもやや控えめな価格帯で選ばれることが多く、
缶詰やお茶のセット、簡素な果物かごなどがよく選ばれます。
会社関係・法人から贈る場合(5,000〜20,000円程度)
取引先や職場の同僚・上司などの関係で供物を贈る場合は、関係の深さと立場に応じて金額が変わります。
-
一般社員が個人として贈る → 3,000円〜5,000円
-
部署や職場の有志連名 → 10,000円前後
-
会社として正式に贈る → 10,000円〜20,000円
この場合、企業名+代表者名を記載する形で表書きに連名するのが一般的です。
また、企業名義の供物は供花が選ばれることが多いですが、供物でも問題ありません。
供物料(現金)を包む場合の金額目安
供物の代わりに「供物料」として現金を包む場合も、金額は同様に3,000〜10,000円程度が妥当です。
-
遠方からで物を贈れない場合
-
「供物辞退」とされている場合でも、何か気持ちを伝えたいとき
-
葬儀前後に直接会えないが、何か届けたいとき
香典とは別に包むのがマナーで、表書きは「御供物料」「御供」などが一般的。
封筒には不祝儀用の黒白の水引を用い、新札は避けるのが基本です。
金額よりも「気持ちと場に合った選び方」が大切
供物の金額にはある程度の相場はありますが、金額よりも大切なのは気持ちの伝わる贈り方です。
-
故人や遺族との関係性
-
贈るタイミングや状況
-
地域や宗教の慣習
これらを総合的に考えて、「無理のない範囲で、心のこもった供物を選ぶ」ことが、何よりの供養となります。
供物を選ぶ際によくあるQ&A
葬儀の供物について調べていると「こういうときはどうすれば?」という細かな疑問が出てくるものです。
このセクションでは、供物に関してよくある代表的な質問に、Q&A形式でお答えします。
Q. 供物を「辞退」されていた場合はどうすればいい?
A. 素直に辞退の意向を尊重し、無理に贈らないのがマナーです。
最近では、「供物・供花・香典はご遠慮ください」といったアナウンスがされる葬儀も増えています。
その場合、供物を贈ることで遺族に返礼や対応の負担がかかってしまうため、気持ちだけ伝えるのが最もスマートな対応です。
どうしても何かしたい場合は、後日あらためて手紙や一言メッセージなど、負担にならない形で思いを届けるとよいでしょう。
Q. 複数人で連名にしても問題ない?
A. はい、問題ありません。
供物を連名で贈ることはよくあることで、同僚・友人グループ・親族一同など、関係性を明記したうえで贈るのが一般的です。
ただし、以下の点にご注意ください。
注意ポイント
-
名前は3名以内なら全員記載、それ以上なら「〇〇一同」とする
-
表書きに収まりきらない場合は別紙に名前一覧を添える
-
個人名を並べる場合は、目上の人から順に書く
Q. 供物と供花を両方贈ってもいいの?
A. 基本的には問題ありません。ただし、贈る前に喪主や葬儀社への確認が無難です。
供物と供花を両方手配するケースは、特に故人と深い関係があった場合や、企業・団体として贈る場合などに見られます。
ただし、会場によっては「供花の数に制限がある」「祭壇スペースの都合上、供物は一部のみ飾る」などのケースもあるため、事前確認は必須です。
Q. 通夜と告別式、どちらに供物を贈るべき?
A. 基本的には「通夜前に届く」ように贈るのが理想です。
供物は通夜や告別式の祭壇に飾られることが多いため、通夜当日の午前〜前日までに届くよう手配するのが望ましいです。
手配が間に合わない場合は、葬儀社に相談のうえ、式後に弔意を伝える形にしても問題ありません。
Q. 供物が間に合わなかったときはどうすれば?
A. 焦らず、後日「お悔やみの品」や「供花」「供物料」を贈るのも選択肢です。
やむを得ず葬儀に間に合わなかった場合でも、
後日改めて自宅宛に供物やメッセージを送ることで、誠意を伝えることができます。
この場合は、香典返しのタイミングを避けるよう注意しつつ、
「ご葬儀に伺えず失礼いたしました。ささやかながら…」というような一言を添えると、より丁寧です。
まとめ|供物は心を形にした贈り物
葬儀の供物は、単なる贈り物ではなく、故人への祈りと、ご遺族への配慮を込めた心の表現です。
宗教や地域の違いがある中で、「正解がわからない」と悩む方も多いかもしれませんが、
何より大切なのは、形式にとらわれすぎず、相手の立場に寄り添った選び方をすることです。
本記事では、以下のようなポイントを解説してきました。
-
供物の意味と供花との違い
-
食品・飲料・お線香・供物料などの主な種類
-
宗派・地域性・故人の人柄を意識した選び方
-
手渡し・配送時のマナーとタイミング
-
相場の目安と、関係性に応じた贈り方
-
よくある疑問とその対応方法
葬儀の場では、言葉にできない想いを供物で伝える場面も少なくありません。
だからこそ、「何を贈るか」だけでなく、「どう贈るか」「なぜ贈るか」という姿勢そのものが、供養の一部となります。
そして何より、供物を通じて大切なのは、
故人を思う気持ちを忘れずに、相手を思いやる心を形にすること。
難しいと感じたら、一度立ち止まり、
「自分が受け取る側だったらどう感じるだろうか」と想像してみると、きっと答えが見つかるはずです。
葬儀の場で、あなたのその想いがきちんと伝わり、
故人への敬意とご遺族への配慮が届きますように。