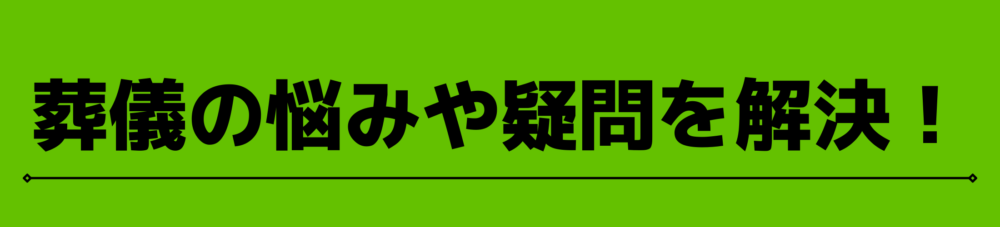「生活保護を受けていたら、葬儀なんてできないのでは…」
「もし身内が亡くなったら、どうすればいいの?」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
確かに、葬儀には一定の費用がかかります。
一般的な葬儀でも数十万円は必要とされ、生活保護を受給している世帯にとっては、非常に大きな負担となり得ます。
しかし実際には、生活保護受給者であっても、きちんと葬儀を執り行える制度が用意されています。
それが「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という仕組みです。
葬祭扶助は、経済的に困窮していても、最低限の葬儀を行えるよう支援してくれる公的制度。
申請さえ正しく行えば、火葬や必要最小限の葬送にかかる費用を自治体が負担してくれる可能性があります。
この制度を知っているかどうかで、「最期のお別れ」の在り方は大きく変わります。
この記事では、
-
葬祭扶助とは何か?
-
どんな人が対象になるのか?
-
どのように申請すればいいのか?
といった点を、わかりやすく丁寧に解説していきます。
生活保護を受けている方や、そのご家族にとって少しでも安心につながる情報となれば幸いです。
目次
生活保護を受けていると葬儀はできないの?
「生活保護=経済的に困窮している」という状況から、
「亡くなったときに葬儀をあげることはできないのでは?」と考えてしまう方は少なくありません。
実際、ご遺族の中には費用がネックとなり、葬儀そのものをあきらめかけるケースもあるようです。
ですが、結論からお伝えすると――
生活保護を受けていても、一定の条件を満たしていれば、葬儀は可能です。
そのための公的支援制度が「葬祭扶助(そうさいふじょ)」です。
葬祭扶助は、生活保護制度の一環として設けられているもので、
経済的に厳しい状況にある方でも、人としての尊厳を持って最期を迎えるための最低限の葬儀費用を支給してもらえる制度です。
たとえば――
-
ご本人が生活保護を受けていた
-
ご遺族(喪主となる人)が生活保護受給者で、葬儀費用を捻出できない
-
その他、扶養義務者(家族)も経済的に厳しく支援ができない
こうした条件に当てはまる場合、火葬や搬送、棺などにかかる費用を自治体が負担してくれる可能性があります。
ただし注意点として、葬祭扶助によって行える葬儀は、あくまでも「最低限のもの」に限られます。
注意ポイント
-
通夜・告別式なし(※形式としての儀式は行われない)
-
火葬式(直葬)スタイルが基本
-
会食や香典返しなどの接待要素は対象外
-
支給金額も20万円前後が上限目安
つまり、「見送る気持ちは込めるが、贅沢な演出はできない」というのが現実です。
「生活保護=葬儀は無理」と思い込んでしまい、制度の存在を知らずに葬儀をあきらめたり、無理な借金をしてしまう方も少なくありません。
だからこそ、事前に“葬祭扶助”の存在を知っておくことが、精神的にも金銭的にも大きな安心材料になります。
次の章では、この葬祭扶助という制度が具体的にどういったものなのか、支給内容や対象条件について詳しく解説していきます。
葬祭扶助とは?
「葬祭扶助(そうさいふじょ)」とは、生活保護制度の一環として設けられている、最低限の葬儀費用を公的に支援する制度です。
経済的な事情で葬儀を行えない人のために、火葬や搬送、棺などの費用を自治体が負担してくれるもので、
人としての最期の尊厳を守るために設けられた制度といえます。
葬祭扶助は、「経済的理由で弔いの場が持てない」ことによって起こる社会的孤立や混乱を防ぎ、
誰もが最低限の形で見送られる権利を保障することを目的としています。
生活保護を受給していた方はもちろん、遺族側が経済的に困窮している場合にも、一定の条件下で利用できます。
「支援を必要とする人が、最後まで人間らしく生きられるようにする」
それが葬祭扶助の根本的な理念です。
葬祭扶助が適用される主な例としては、次のようなものがあります。
-
故人が生活保護を受給していた
-
喪主または葬儀の手続きを行う人が生活保護受給者で、葬儀費用を支払えない
-
故人も喪主も生活保護は受けていないが、扶養義務者の援助が受けられず、経済的に困窮している
つまり、「葬儀費用を支払う経済的余裕が一切ない」と判断されれば、支援の対象となる可能性があります。
支給される金額は自治体によって若干異なりますが、おおむね20万円前後が一般的な支給額とされています。
実際に葬祭扶助でカバーされる費用には以下のようなものがあります。
-
棺(ひつぎ)
-
遺体の搬送(自宅や施設から火葬場などへ)
-
火葬料金(火葬場の使用料)
-
骨壺・骨箱
-
ドライアイス・保冷処置(簡易的なもの)
これらは、葬儀社が作成した「見積書」に基づいて、福祉事務所が妥当かどうかを審査した上で支給されます。
確かに、葬祭扶助で実施されるのは、いわゆる直葬に近い簡素な内容です。
ですが、「火葬すらできないのでは」という不安を抱える方にとっては、最低限のセレモニーが可能になる大切な制度です。
大切なのは、この制度を知っておくこと・必要なときに正しく活用できること。
次は、実際にこの制度を利用するための「申請条件」と「注意点」について詳しく見ていきましょう。
葬祭扶助を利用するための条件とは?
葬祭扶助は、生活保護制度の一環として国が定めた制度ですが、誰でも必ず利用できるというものではありません。
あくまで「葬儀費用を支払うことが困難な事情がある」と認められた場合に限って支給される、いわば緊急時の最低限の支援です。
ここでは、どのような条件を満たしていれば利用が可能になるのかを、代表的な4つのパターンに分けて詳しく解説します。
1. 故人が生活保護受給者だった場合
これは最もわかりやすいパターンです。
亡くなられたご本人が生前、生活保護を受けていた場合、葬祭扶助の対象となる可能性は非常に高いです。
生活保護を受けていたということは、経済的に困窮していた証拠でもあるため、
自治体も「本人が葬儀費用を用意できたはずがない」という前提で判断を進めてくれます。
ただし、ここで重要になるのが喪主(葬儀を行う人)の経済状況です。
遺族や親族に資産や高収入があると、福祉事務所から「葬祭扶助の対象外」とされることもあります。
ポイント
故人が生活保護を受給していた場合でも、
・喪主が経済的に余裕がある
・高収入の子どもや親族がいる
という場合は却下される可能性あり。
2. 喪主(申請者)が生活保護受給者の場合
故人が生活保護を受けていなかったとしても、喪主となる人が生活保護を受けている、またはそれに近い困窮状態にある場合も、葬祭扶助の対象になる可能性があります。
たとえば――
-
生活保護を受けている方が、親や兄弟の葬儀を執り行うことになった
-
高齢の母親を亡くし、年金だけで生活している自分に費用の余裕がない
-
離れて暮らしていた身内が亡くなったが、自分自身もシングルでパート収入だけ
このようなケースでは「自分自身の生活を保つのが精一杯で、葬儀費用はとても払えない」という状況があれば、制度を利用できる可能性があります。
なお、生活保護を受けていなくても「収入が非常に低く、貯蓄もない」ことが明確であれば、ケースバイケースで柔軟に判断されることもあります。
3. 扶養義務者からの支援が得られない場合
扶養義務者(たとえば子どもや親、兄弟姉妹など)が存在していても、
- 連絡が取れない
- 支援を拒否されている
- そもそも扶養義務者自身も困窮している
という場合は、葬祭扶助が認められるケースもあります。
福祉事務所は、必ず支援してくれる人はいないかを調査します。
このときに必要になるのが「扶養照会」と呼ばれる確認手続きです。
扶養照会によって、「経済的な援助が見込めない」と判断されれば、葬祭扶助が通る見込みが出てきます。
注意ポイント
扶養義務者がいる場合、「その人が本当に支援できないのか」を見極めるため、
所得証明書や住民票の提出を求められることもあります。
4. 自治体が定める困窮状態の基準を満たしていること
葬祭扶助の判断基準は、全国で統一されているわけではなく、最終的な判断は各自治体(福祉事務所)に委ねられています。
つまり、「東京では通ったけど、別の市では通らなかった」というケースもゼロではありません。
そのため、以下の点に注意しましょう。
-
対象範囲や必要書類は自治体によって異なる
-
葬儀前に申請しないと対象外になることが多い
-
誰が喪主か、どこまでの親族か、という関係性も判断材料になる
困ったときは、「これは無理かも…」と思っても、まずは福祉事務所に相談することが大切です。
実際のケースでは、「一度相談してみたら通った」という例も多く見られます。
繰り返しになりますが、葬祭扶助は事前に申請することが絶対条件です。
申請せずに葬儀を行ってしまった場合、たとえ条件を満たしていたとしても、後から支給してもらうことはほぼ不可能です。
万が一のときは、「まずは福祉事務所に電話」この流れを覚えておきましょう。
葬祭扶助の申請手順
葬祭扶助は、生活保護を受けている方や経済的に困窮している方が、最低限の葬儀を行うために利用できる制度ですが、申請の流れやタイミングを間違えると支給されないこともあるため注意が必要です。
ここでは、葬祭扶助を受けるための一連の流れを、わかりやすく4つのステップでご紹介します。
① 福祉事務所(生活保護課)へ相談・連絡する
まず何よりも大切なのが、「葬儀を行う前に福祉事務所へ相談すること」です。
これを怠ってしまうと、原則として葬祭扶助の対象外になってしまいます。
たとえば――
-
先に葬儀を依頼してしまった
-
火葬や搬送を済ませてしまった
-
葬儀社に契約金を支払った
こうした状況では、「自己判断で支出した」と見なされ、後から申請しても認められない可能性が非常に高くなります。
注意ポイント
亡くなったらまず、すぐに市区町村の福祉事務所(生活保護担当窓口)へ連絡を。
「これから葬儀をするつもりなのですが、葬祭扶助を使いたい」と伝えましょう。
② 必要書類をそろえて提出する
福祉事務所で相談を行ったあとは、所定の書類を提出する必要があります。
自治体によって多少異なりますが、主に以下のようなものが必要になります。
提出が求められる主な書類は以下の通りです。
-
葬祭扶助申請書(窓口で記入・もしくは指定書式)
-
故人の死亡診断書または死体検案書のコピー
-
申請者(喪主)の身分証明書
-
故人との関係性を証明する書類(住民票や戸籍など)
-
葬儀社が作成した見積書
-
預貯金や収入状況がわかる資料(申請者および扶養義務者)
見積書については「扶助対象となる範囲に収まっていること」が前提となるため、必ず扶助制度に対応した葬儀社に見積もりを依頼しましょう。
③ 福祉事務所による審査
申請が完了すると、福祉事務所が支給の可否を審査します。
この際、以下のような点が確認されます。
-
故人や申請者の生活状況・収入・資産状況
-
扶養義務者の有無と援助の可否
-
見積書の内容が制度の上限を超えていないか
-
緊急性や必要性の妥当性
審査には通常、即日〜数日程度の時間を要しますが、火葬の日程が差し迫っている場合は、迅速に対応してもらえることもあります。
そのためにも、できるだけ早めの相談が大切です。
④ 指定葬儀社による簡易葬儀の実施
審査が通り、支給が決定すると、原則として自治体と連携している指定葬儀社によって葬儀が執り行われます。
葬祭扶助で行える葬儀の形式は、おおむね以下のような内容となります。
-
通夜や告別式なし(火葬式・直葬)
-
遺体搬送・棺・火葬・骨壺等の最低限の内容
-
式場は使用せず、火葬場へ直接向かうケースが多い
-
会食・香典返しなどの儀礼的な要素は対象外
また、葬儀社との間でトラブルを避けるためにも、扶助の範囲外のオプションを勝手に追加しないように気をつけましょう。
葬儀を急いで手配しなければならない事情があるとき、
つい先に民間の葬儀社に連絡してしまう方もいます。
その場合でも、支払いをする前であれば、福祉事務所を通して調整してもらえる可能性があります。
ただし、「契約を交わした」「前金を支払った」となると、葬祭扶助の対象外になってしまうため、
少しでも迷ったら、とにかく先に福祉事務所に相談してください。
葬祭扶助を利用する際の注意点
葬祭扶助は、経済的な理由で葬儀を行うことが難しい人のために用意された大切な制度ですが、
申請のタイミングや手順、制度の正しい理解を欠くと、「支給されなかった」「余計な費用が発生した」といったトラブルにつながることもあります。
以下に、実際によくあるミスや誤解を踏まえた「利用時の注意点」をまとめました。
① 必ず葬儀前に申請を行うこと
葬祭扶助で最も重要なのは、申請のタイミングです。
「亡くなってすぐに慌てて葬儀を手配してしまった」「火葬だけでも進めてしまった」
こうした場合、たとえ条件を満たしていたとしても、支給対象外となる可能性が高くなります。
ポイント
少しでも迷ったら、まずは市区町村の福祉事務所へ連絡。
「葬儀の準備を始める前」に相談することが絶対条件です。
② 自由な葬儀プランは選べない
葬祭扶助は、最低限の内容に限定された直葬スタイルが基本です。
通夜・告別式・会食・返礼品など、一般的な葬儀のような形式は行われません。
-
自宅での安置やセレモニー会場の利用
-
僧侶を呼んで読経を依頼する
-
花や遺影、特別なオプションをつける
これらはすべて「自己負担」であり、扶助の範囲を超えた部分は認められません。
制度を利用するうえでは、「質素な見送りになる」ことを理解した上で利用することが大切です。
③ 指定業者以外での手配は原則不可
多くの自治体では、あらかじめ福祉事務所と契約を結んでいる葬儀社(指定業者)が葬祭扶助を実施します。
そのため、民間の葬儀社に直接依頼した場合、扶助制度に対応していないことがあります。
注意ポイント
- 葬祭扶助を使いたい場合は、福祉事務所を通して紹介される葬儀社に依頼する
- 勝手に契約すると、全額自己負担になる可能性あり
葬儀社に相談する前に、「扶助制度対応の葬儀社かどうか」を福祉事務所に必ず確認しましょう。
④ 一部自己負担が発生するケースもある
基本的には全額支給の制度ですが、次のような場合には一部自己負担が発生する可能性があります。
-
親族から香典や支援金を受け取った場合
-
支給範囲を超えたオプションを利用した場合
-
扶助対象の上限金額を超える見積もりになった場合
このようなケースでは、超過分を自費で支払う必要があります。
「完全に無料」と思い込まず、制度の範囲内で進める意識を持つことが重要です。
⑤ 周囲の理解・サポートも得られるようにする
「葬祭扶助を使うなんて恥ずかしい…」という気持ちになる方もいるかもしれません。
ですが、これは国が正式に認めた支援制度であり、誰かに迷惑をかけているわけではありません。
もし親族や周囲から反対の声があったとしても、
制度の目的を説明し、自分が責任を持って故人を見送る手段として堂々と活用して構いません。
制度の理解が深まれば、周囲も納得しやすくなり、サポートしてくれる人も出てくるはずです。
葬祭扶助は、制度としてはしっかり整っていますが、
使い方を間違えると「こんなはずじゃなかった…」という結果にもなりかねません。
だからこそ、
-
自分は利用できるのか?
-
どこに連絡すればいいのか?
-
何を準備しておくべきか?
迷ったときは、福祉事務所へ相談することが何よりの第一歩です。
まとめ|生活保護でも葬儀をあきらめる必要はない
経済的に苦しい状況にある中で、身内や身近な人を見送らなければならない。
その現実に直面したとき、「自分には葬儀なんて無理かもしれない」と不安になるのは当然のことです。
ですが、そうした人のために用意されているのが、「葬祭扶助」という制度です。
これは国が正式に認めた支援制度であり、条件を満たしていれば、生活保護を受けていても、また受けていなくても、最低限の葬儀を公費で行うことが可能になります。
人が亡くなるということは、誰にとっても大切で、かけがえのない出来事です。
経済的な事情がどうであれ、故人に対する感謝や敬意、そして別れの時間は必要不可欠です。
葬祭扶助は、決して特別な人だけのための制度ではありません。
誰もが、どんな状況でも人としての最期をきちんと見送ることができるために設けられた、最低限の権利を守るための制度なのです。
葬祭扶助があることを知らなければ、
- 葬儀をあきらめてしまったり
- 借金をしてまで無理に葬儀を行ってしまったり
- トラブルに巻き込まれてしまったり
そんな悲しい結果を招くこともあります。
ですが、制度の存在を知り、正しい手順で申請することで、
あなた自身も、故人も、穏やかに心を整えてお別れの時間を迎えることができるのです。
制度は複雑に見えても、最初の一歩はとてもシンプルです。
「もしものときに、葬儀をどうすればいいか不安なんです」
そう伝えるだけで、必要な情報や手続きの流れを案内してくれます。
どうか、あきらめずに。
そして、あなた自身やご家族が安心して見送れるよう、制度を「遠慮なく」「堂々と」活用してほしいと願っています。